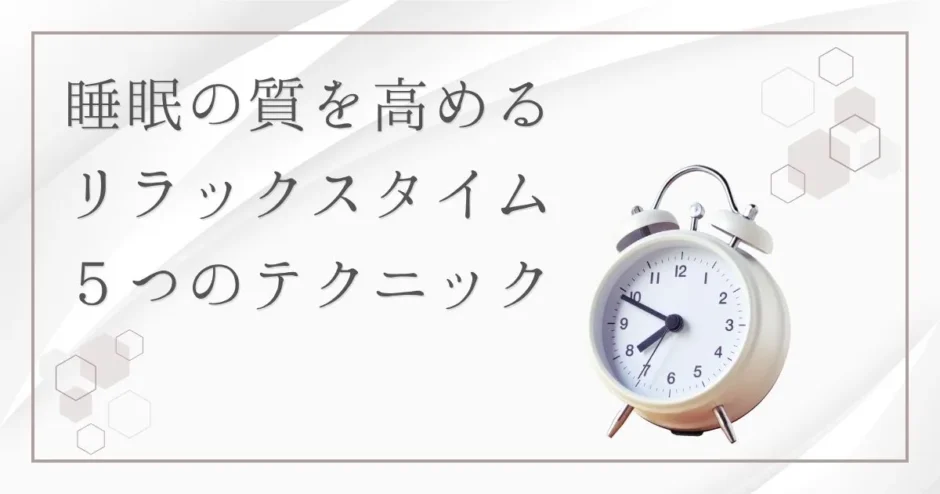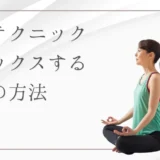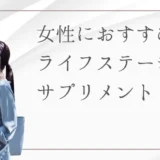「夜、布団に入ってもなかなか眠れない…」
「寝ても途中で目が覚めてしまう…」
「朝起きても疲れが取れない…」
こんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
現代人は仕事や人間関係、情報過多によるストレスなど、さまざまな要因で眠りの質が低下しがちです。
だからこそ、寝る前の過ごし方を少し工夫して、睡眠の質を少しでも高めたくありませんか?
特に「リラックスタイム」を意識的に取り入れるのは、快眠への近道です。
今回は、音楽やアロマ、ストレッチ、入浴、空間作りといった、寝る前に取り入れやすい5つのリラックステクニックをご紹介します。
また、リラックスタイムに役立つとされているマグネシウムの働きや摂取方法についても解説するので、快適な睡眠を目指したい方はぜひ参考にしてください。
寝る前にリラックスする5つのテクニック

それではさっそく、誰でも手軽に取り入れられる5つのリラックステクニックをご紹介します。
毎晩のルーティンに加えて、自然と眠りに入りやすい環境作りを目指しましょう!
1.音楽を聴く
眠る前に静かに音楽を流すことは、手軽に取り入れやすいリラックス法の一つです。
音楽は自律神経に働きかけ、緊張をほぐし心拍数を落ち着ける働きがあるとされています。
イヤホンではなくスピーカーや枕元のオーディオを活用すれば、体を締め付けず自然にリラックスしやすいのでおすすめです。
寝る前の時間に、静かで落ち着いた音楽を流すだけで、心と体は自然と睡眠モードへと切り替わります。
おすすめは、ベッドに入る30分前から音量を小さめに設定し、部屋全体にやさしく響かせること。
イヤホンやヘッドホンを避け、スピーカーやスマートスピーカーから流すと、耳や頭部に負担がかかりません。
リラックスを目的にするため、作業用BGMや歌詞が多い音楽ではなく、静かなインストゥルメンタルを選ぶのがコツです。
- 心拍数が下がり、自然な眠気を誘う
- 副交感神経が優位になりリラックスできる
- ストレスや不安感を和らげる
- 睡眠の導入時間を短縮する
- 深い眠り(ノンレム睡眠)が得やすくなる
- クラシック(モーツァルト、バッハなどの穏やかな曲)
- ヒーリングミュージック(自然音、波の音、雨音など)
- アンビエント音楽
- ピアノソロやアコースティックギターのインストゥルメンタル
- 432Hz音源など心を落ち着ける周波数の音楽
ロックやテンポの速いダンスミュージックは心拍数を上げ、交感神経を刺激してしまうため、逆に眠りを妨げる可能性があります。
睡眠前は、心が穏やかになる音楽を意識的に選ぶことが大切です。
音楽は脳の「報酬系」に働きかけ、快楽物質であるドーパミンやセロトニンの分泌を促します。
これにより気分が安定し、不安や緊張がやわらぎます。
また、ゆったりとしたテンポの音楽は脳波をアルファ波やシータ波へと導き、心を落ち着かせ、眠気を自然に引き出します。
一部の研究では、音楽療法は睡眠障害の改善やストレス軽減に有効であることが報告されており、安心して取り入れられるリラックス習慣の一つといえるでしょう。
2.アロマを楽しむ
一日の疲れや緊張を和らげるには、香りの力を借りるのも効果的です。
心地よいアロマの香りは、脳や神経に直接働きかけ、自然に心を落ち着かせてくれます。
寝る前にお気に入りの香りを取り入れることで、安心感に包まれながらスムーズに眠りへと移行できるでしょう。
寝る前にアロマを取り入れることで、香りの力が自律神経に働きかけ、自然な眠気をサポートしてくれます。
方法はとてもシンプルで、アロマディフューザーやアロマランプで精油を焚く、枕元にアロマストーンを置く、またはコットンに数滴垂らして枕元に置くだけでも効果的です。
お風呂に数滴落とす方法もおすすめで、体を温めながら香りでリラックスすることができます。
- 自律神経を整えて副交感神経を優位にする
- ストレスや不安を軽減し、心を落ち着ける
- 睡眠までの時間を短縮する
- 睡眠の質を高める(中途覚醒を減らす)
- リラックス感から深い呼吸を促す
- ラベンダー:心を落ち着かせ、入眠をサポート
- カモミール:不安を和らげ、穏やかな気分に導く
- ベルガモット:柑橘系でリフレッシュしつつリラックス効果
- サンダルウッド:深い落ち着きと瞑想的な安らぎ
- オレンジスイート:気持ちを明るくし、安心感を与える
刺激的な香りや甘すぎる香りは逆に脳を活性化させてしまうことがあります。
入眠に向くのは、ラベンダーやカモミールのようにリラックスしやすい香りですが、選ぶ際には、心地よいと感じるかどうかを基準にするのも大切です。
香りは好みによって効果の感じ方が違うため、自分に合うアロマを見つけると良いでしょう。
アロマの香り成分は、鼻から脳へ直接伝わり、大脳辺縁系や自律神経系に作用するとされています。
特にラベンダーには鎮静作用や筋肉の緊張をほぐす働きがあり、睡眠導入効果が一部の研究でも認められています。
また、嗅覚は五感の中でも記憶や感情に直結しやすいため、「安心する香り」を取り入れることで心理的にも眠りに入りやすくなるのです。
3.ストレッチ・ヨガを行う
就寝前にリラックスタイムを設けるには、一日の終わりに軽いストレッチやヨガを取り入れるのがおすすめです。
ストレッチやヨガは、心身をゆるめて睡眠に備えるのに最適で、デスクワークや立ち仕事で凝り固まった筋肉をほぐすのにも役立ちます。
また、深い呼吸を伴うヨガは精神的な安定をもたらし、気持ちを落ち着けてくれるでしょう。
寝る前のストレッチは5〜10分程度で十分です。
ベッドの上や寝室の床で、ゆったりと呼吸を意識しながら体を伸ばしましょう。
首や肩、腰回り、足の裏側など、日中の疲れがたまりやすい部分を中心にほぐすと効果的です。
ヨガの場合は、難しいポーズに挑戦する必要はなく、リラックスを目的にした基本的なポーズで十分。
大切なのは無理をせず、心地よさを感じながら行うことです。
- 筋肉の緊張を和らげ、血流を改善する
- 副交感神経を優位にし、リラックス効果を高める
- 呼吸が深まり、不安感や緊張を軽減する
- 体温の自然な下降を助け、入眠をスムーズにする
- 睡眠中の体の回復力を高める
- 首の側面や肩回りをゆっくり伸ばすストレッチ
- 前屈(立位でも座位でもOK、背中と脚の裏を伸ばす)
- 猫のポーズ(四つんばいで背中を丸めたり反らしたり)
- チャイルドポーズ(おでこを床につけて背中を伸ばす)
- 仰向けで膝を抱えるポーズ(腰や背中をほぐす)
寝る前は交感神経を刺激しないことが重要です。
強い筋トレや激しいヨガは体を覚醒させてしまうため、避けたほうが良いでしょう。
リラックスを目的にしたストレッチやヨガを選び、深い呼吸を意識して「心地よい」と感じる範囲で行うと、快眠につながりやすくなります。
ストレッチやヨガを行うと、筋肉の緊張が和らぎ血流が促進されます。これにより体温調整がスムーズになり、眠りに入りやすくなるのです。
また、呼吸を深めることで酸素の取り込みが増え、副交感神経が優位になり心拍数が落ち着きます。
ヨガの瞑想的な効果はストレスホルモンの分泌を抑制し、心理的にも安心感を与えてくれるため、睡眠の質の向上に役立つと一部の研究において報告されています。
4.入浴でリフレッシュする
一日の緊張をほどく時間としての入浴は、寝る前のリラックス習慣に取り入れやすい方法です。
お湯につかる心地よさは、心身をゆるめて睡眠モードへ切り替える助けになります。
体調に合わせて無理のない範囲で行いましょう。
就寝の1~2時間前に、ややぬるめのお湯で10~15分程度の入浴を目安にします。
湯温は目安として38~40度前後。
肩までどっぷり浸かる全身浴のほか、暑い季節や時間がないときは半身浴や足湯も取り入れやすい方法です。
入浴後は強い照明を避けて、静かな音楽やアロマと組み合わせるとより落ち着きやすくなります。
- 体のこわばりをゆるめて気分を落ち着ける
- 寝つきやすいコンディションづくりを助ける
- 心地よい温熱感でリラックスしやすくなる
- 手足のめぐりを意識しやすくなる
- 就寝前のルーティンとして気持ちの切り替えに役立つ
- ぬるめの全身浴 10~20分
- 半身浴でゆっくり呼吸に集中する
- 足湯をしながら読書やストレッチを軽く行う
- 入浴後は部屋を暗めにして静かな時間を過ごす
- 清涼感の強すぎる入浴剤は夜は控えめにする
エプソムソルトなど、マグネシウム由来の入浴料はお湯の感触をやわらかく感じやすいという声が多く、自宅で気軽にリラックス時間を演出しやすいのが魅力です。
香りの強すぎないタイプを選び、就寝前に刺激を与えすぎないように使うと良いでしょう。
入浴で体が温まると、湯上がりに体表面の熱がゆるやかに放散され、自然と落ち着きやすい状態へ移行すると考えられています。
お湯の浮力や水圧は負担を感じにくく、呼吸が深まりやすい点もリラックスにつながります。
マグネシウム由来の入浴料は、香りや肌触りといった感覚面を通じてくつろぎを演出しやすく、就寝前の環境作りとして取り入れられています。
いずれも個人差がありますので、心地よさを基準に調整しましょう。
5.リラックス空間を演出する
寝室を「休むための場所」として整えることは、入眠をスムーズにするための大切な準備です。
特別な道具をそろえなくても、光や音、香りなどを工夫することで落ち着きやすい空間がつくれます。
寝る前には、照明を暗めにして暖色系の光に切り替え、スマホやパソコンの使用を控えましょう。
余計なものを視界から減らし、落ち着いた音や香りを取り入れると安心感が高まりやすくなります。
ベッド周りを整えることも「これから休む時間」という合図になります。
- 心身を落ち着けやすくなる
- 入眠の流れをスムーズにしやすくなる
- 途中で目覚めても再び休みやすくなる
- 翌朝の目覚めをサポートする
- 日々の習慣化により「眠るスイッチ」を入れやすくなる
- 照明を落とす(間接照明やキャンドル風ライトなど)
- スマホやPCを寝室に持ち込まない
- SNSやメールの返信をやめ、静かな時間をつくる
- リラックスできる音(自然音や小さなBGM)を流す
- 香りを控えめに取り入れる(ラベンダーやカモミールなど)
- 寝具の触感を整える(やわらかいシーツや肌触りの良いパジャマ)
- 室温・湿度を調整する(やや涼しいと感じる目安)
ポイント「雰囲気作り」は「安心作り」
大切なのは「刺激を減らすこと」と「安心できる雰囲気をつくること」です。
強い光や大きな音は覚醒につながるので控えるようにし、逆に心地よい香りや柔らかな触感を少しずつ足していきましょう。
光が弱まると脳内の覚醒信号が抑えられ、休息へ移行しやすくなりますし、静かな音や落ち着いた香りは自律神経の切り替えを助けます。
また、毎晩同じ流れで寝室を整えることは条件反射のように「ここは休む場所」と脳に認識させやすく、自然に眠りへ導くサポートになります。
就寝前のリラックス法として、もう一つおすすめしたいのが「読書」です。ただし、電子書籍ではなく紙の本を選びましょう。その理由は、スマートフォンやタブレットの画面に含まれるブルーライトを避けられるからです。ブルーライトは脳を刺激し、眠気を妨げる原因となります。
理想的なのは、やわらかな照明のもと、ベッドに入りながら紙の本をゆっくり読むこと。ページをめくる静かな時間が心を落ち着かせ、自然と眠気が訪れるのを感じられるでしょう。また、子どもにとっても就寝前の読書や読み聞かせは、心を穏やかにし、安眠を促す効果があるといわれています。
睡眠の質を高める5つのコツ

快適な眠りは、寝る前のリラックスだけでなく、日中の過ごし方や生活リズムにも大きく左右されます。
ここでは、今日から意識できる5つのコツをご紹介します。
1.朝日を浴びる
朝の光を浴びることは、体内時計を整える最も自然な方法の一つです。
起床後にカーテンを開けて日差しを取り入れるだけでも、体は「朝が来た」と認識しやすくなります。
可能であれば短い散歩を取り入れると、気分のリフレッシュにもつながるでしょう。
2.概日リズムを意識する
概日リズムとは、わかりやすくいうと“体内時計”のことです。
食事・運動・入浴・就寝などの時間やリズムを毎日ある程度一定に保つことは、体内のリズムを安定させるために役立ちます。
リズムが乱れると入眠が難しくなったり、夜中に目が覚めやすくなったりすることもあるため、「できるだけ同じ時間帯」を意識しましょう。
3.寝だめをしない
休日に長時間眠る「寝だめ」は、一時的には楽に感じても、その後のリズムを崩す原因になりやすいといわれています。
理想は平日と休日の起床時間を大きく変えないこと。
眠気が強いときは昼間の短い仮眠で調整すると、夜の睡眠に影響を与えにくくなります。
4.運動する
日中に体を動かすことは、夜の休息を整えるサポートになります。
ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど無理のない範囲で取り入れてみましょう。
夜遅くの高強度運動は交感神経を刺激することがあるため、夕方までの時間帯に行うのがおすすめです。
5.生活習慣を見直す
規則正しい生活リズムや栄養バランスのとれた食事は、良質な睡眠を作る基本です。
特にミネラルやビタミンを意識的に取り入れることが大切です。
中でもマグネシウムは、体や神経の働きを支える栄養素であり、食事に取り入れることで日々のリラックス習慣のサポートにつながります。
豆類、ナッツ、海藻、野菜などに多く含まれるため、少しずつ食卓に加えてみましょう。
マグネシウムがリラックスに役立つ理由

私たちの体に欠かせないミネラルの一つであるマグネシウムは、エネルギー代謝や筋肉、神経の働きを支える重要な存在です。
近年では、ストレス対策や休息のサポートにおいても注目されており、睡眠との関わりが研究で示されています。
ここからは、マグネシウムの基本的な働きと、現代人に不足しやすい理由を整理していきましょう。
マグネシウムの基本的な働き
マグネシウムは、体の中で800種類以上の酵素反応に関わるといわれる重要なミネラルです。
エネルギーを生み出す代謝、筋肉の収縮と弛緩、神経伝達の調整など、日常生活に欠かせない機能を幅広く支えています。
特に注目されるのは、マグネシウムが神経伝達物質のバランスを保つ役割を持ち、リラックス時に優位になる副交感神経の働きにも関与しているとされている点です。
また、筋肉が過度に緊張しないよう調整する作用もあり、心身を休息に向かわせる土台として大切な栄養素といえます。
つまりマグネシウムは、エネルギーを支える一方で、休息やリラックスを整える「陰と陽」の両面に関わる存在なのです。
マグネシウムの働きについては、「マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法」で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
 マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説
マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説
現代人にマグネシウムが不足しがちな理由
本来マグネシウムは、海藻や豆類、ナッツ、野菜などに豊富に含まれています。
しかし、現代の食生活では意識していないと不足しやすいといわれています。
その大きな理由の一つが、精製食品の増加です。
白米や精製小麦粉は食べやすい一方で、精製過程でマグネシウムが取り除かれてしまいます。
また、外食や加工食品に頼る機会が増えると、自然とマグネシウムを含む食品の摂取量が減りがちです。
さらに、ストレスや過度な飲酒、カフェインの摂りすぎなどは、体内のマグネシウム消費や排出に影響を与える可能性があるとされています。
忙しい日々の中で食生活が乱れると、知らず知らずのうちに不足を招きやすくなるのです。
まずは「自分が不足していないか」を振り返ることが、バランス良く栄養を摂取する第一歩です。

マグネシウムを効果的に摂取する方法

ここからは、食事を中心に、サプリメントや入浴料、クリームなど、ライフスタイルに合わせてマグネシウムを上手に取り入れる方法をご紹介します。
食事からマグネシウムを摂取する
マグネシウムを取り入れるなら、日々の食事の栄養バランスに配慮するのが基本です。
特別な食材を探さなくても、マグネシウムは身近な食品に多く含まれています。
ポイントは「少しずつ」「バランスよく」取り入れること。
大きな変化よりも、毎日の積み重ねが大切です。
具体的な工夫例として、以下のポイントを意識してみましょう。
- 主食の白米に雑穀や玄米を混ぜる
- 味噌汁に豆腐やわかめを加える
- 間食に素焼きのナッツを選ぶ
- 野菜は葉物やブロッコリーを意識して添える
- 魚や海藻を週数回取り入れる
特にマグネシウムは以下の食品に豊富に含まれているので、これらをバランスよく意識的に取り入れるのがおすすめです。
- 海藻類(わかめ、ひじき、昆布)
- 豆類(大豆、枝豆、納豆)
- ナッツ類(かぼちゃの種、アーモンド、カシューナッツ)
- 全粒穀物(玄米、オートミール)
- 野菜(ほうれん草、小松菜、ブロッコリー)
- 魚介類(いわし、あさり)
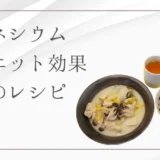 【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選
【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選
サプリメントでマグネシウムを補う
毎日の食事から必要な栄養素をすべてまかなうのは理想的ですが、忙しい生活の中ではなかなか難しいものです。
そのような時に便利なのがサプリメントです。
マグネシウムを含むサプリメントは、手軽に摂取量を補える手段として活用されています。
利用する際は、あくまでも日常の食事を補助する役割であることを意識することが大切です。
基本は食事からの摂取を心掛け、そのうえで不足しがちなときに取り入れるという考え方が望ましいでしょう。
また、摂取量や使用方法は製品ごとの表示に従うことが基本です。
服薬中の方や持病のある方は、事前に医師や薬剤師へ相談してから取り入れるのが安心です。
サプリメントにはクエン酸マグネシウムや酸化マグネシウムなど、吸収のされ方や特徴に違いがあります。
選ぶ時には自分の生活習慣や目的に合っているか、また、続けやすい形状や価格帯かどうかを確認しましょう。
無理なく継続できる方法を見つけることが、サプリメントを賢く活用するポイントです。
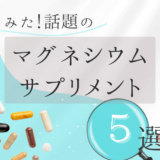 マグネシウムサプリメントのおすすめ5選|吸収率で選ぶ失敗しないコツ
マグネシウムサプリメントのおすすめ5選|吸収率で選ぶ失敗しないコツ
マグネシウム風呂を楽しむ
お風呂は一日の疲れをリセットする大切な時間ですが、そこにマグネシウムを含む入浴料を取り入れると、より心地よいリラックスタイムを演出できます。
エプソムソルトなどのマグネシウム由来の入浴料は、湯に溶かすことでお湯の肌触りがやわらかく感じられることがあり、入浴をより快適な時間に変えてくれるでしょう。
特に就寝前の入浴は、体を温めることで自然な眠気を呼び込みやすい状態を整えるサポートになります。
ただし、肌に合わないと感じた場合や刺激が気になる場合は使用を控えることが大切です。
毎日のバスタイムに無理なく取り入れて、自宅にいながらスパのような雰囲気を楽しんでみてはいかがでしょうか。
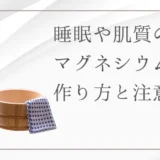 マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法
マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法
マグネシウムクリームを活用する
マグネシウムを手軽に取り入れる方法の一つに、ボディケア用のクリームがあります。
クリームを肌に塗ることで、香りやマッサージの心地よさを通じてリラックスをサポートする習慣として取り入れられています。
就寝前に腕や脚などへ馴染ませると、スキンケアと同時に「休む前の儀式」としても活用できるでしょう。
マッサージをしながら使えば、触覚による安心感や血流の促進を意識しやすくなり、心身をゆるめるきっかけになるのでおすすめです。
また、製品の種類によってはシアバターやココナッツオイルなど保湿成分が含まれており、スキンケアの延長としてアロマを楽しめるものも。
市販のマグネシウムクリームを活用するほか、ニベアやココナッツオイルを使ってマグネシウムクリームを自作することもできます。
自作のマグネシウムクリームは、安価かつ手軽なだけでなく、香りやテクスチャを自分好みにカスタムできるのが魅力。
詳しい作り方については「マグネシウムクリームの2つの作り方|ニベアやココナッツオイルで自作可能!」で紹介しているので、興味のある方はぜひこちらの記事を参考に、オリジナルのマグネシウムクリーム作りに挑戦してみてください。
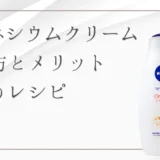 マグネシウムクリームの2つの作り方|ニベアやココナッツオイルで自作可能!
マグネシウムクリームの2つの作り方|ニベアやココナッツオイルで自作可能!
寝る前に摂取する
マグネシウムは一日の中でいつ摂取しても役立つ栄養素ですが、寝る前に取り入れることでリラックスタイムの一部として活用する人もいます。
夕食や就寝前の軽いスナックにマグネシウムを含む食品を選んだり、サプリメントを取り入れたりすると、体を休ませるモードへの切り替えを意識しやすくなるでしょう。
ただし、就寝直前に大量の食事をすると胃腸に負担がかかり、眠りに影響することがあります。
そのため、取り入れる場合は軽めの工夫が望ましいでしょう。
たとえば、ナッツを少量つまんだり、豆乳をコップ一杯飲んだりなど、無理のない範囲で工夫するのがおすすめです。
また、マグネシウムを含むサプリメントを利用する場合は、製品ごとの表示や推奨される摂取タイミングを確認し、ご自分の体質や生活リズムに合わせましょう。
組み合わせを工夫する
マグネシウムは単独でなく、他の栄養素とのバランスを意識しながら摂取するのが大切です。
たとえば、カルシウムとマグネシウムは互いに補い合う関係にあり、筋肉や神経の働きを調整する上で重要な組み合わせとされています。
また、ビタミンDはカルシウムの吸収をサポートする栄養素であり、結果としてマグネシウムと連動しながら体内のバランスを整える助けになると考えられています。
具体的には、魚や乳製品からカルシウムを、きのこ類や日光浴からビタミンDを、そして豆類やナッツ、海藻からマグネシウムを取り入れるといったように、栄養バランスの整った食事を意識すると良いでしょう。
一つの成分に偏らず、全体としてバランスを意識すると、マグネシウムをはじめ、各種栄養素をバランス良く、かつ無理なく続けられる食習慣を築いていけるでしょう。
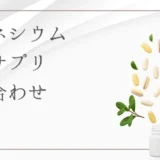 マグネシウムと鉄分のサプリの飲み合わせはNG?上手な摂取方法と注意点
マグネシウムと鉄分のサプリの飲み合わせはNG?上手な摂取方法と注意点
マグネシウムが睡眠に与える影響

マグネシウムは、睡眠にどのような影響を与えるのでしょう。
ここからは、マグネシウムと睡眠の関係について3つの観点から解説します。
セロトニンの産生をサポート
睡眠のリズムを整える上で欠かせないホルモンの一つに「メラトニン」があります。
このメラトニンの原料となるのが、日中に分泌される神経伝達物質「セロトニン」です。
セロトニンがしっかりと作られることで、夜になると自然にメラトニンが生成され、眠りへと移行しやすくなる──という仕組みです。
ここで重要な役割を担っているのがマグネシウムです。
マグネシウムはセロトニンに関わる酵素の働きにも関与する栄養素といわれており、神経伝達の安定に関与しています。
つまり、マグネシウムを十分に摂取することは、セロトニンのスムーズな産生を後押しし、結果的に夜の休息リズムを整えることにつながると考えられるのです。
もちろん効果の感じ方には個人差がありますが、日中の活動でセロトニンをしっかり生み出し、夜に自然な眠気を得るための自然なメカニズムとして、マグネシウムが関与している点は無視できません。
GABAの産生をサポート
脳を落ち着けるために重要な神経伝達物質の一つが「GABA(ギャバ)」です。
GABAは神経の興奮を鎮める役割を持ち、ストレスや緊張で高ぶった心をやわらげる方向に働きかけるといわれています。
この働きによって副交感神経が優位になり、心身が休息モードに入りやすくなるのです。
マグネシウムは、GABAなどの神経伝達物質に関わると言われている栄養素でもあります。
体内に十分な量のGABAがあることで、神経の興奮と抑制のバランスが保たれやすくなり、結果的に落ち着いた状態をサポートすることにつながりやすい──という考え方です。
逆にGABAが不足してしまうと、このバランスが乱れやすくなる可能性があると指摘されています。
そのため、マグネシウムは「夜の休息環境を整えるミネラル」ともいえる存在です。
ストレスを完全になくすことは難しくても、日々の食事や生活習慣でマグネシウムを意識することが、リラックスできる夜を迎える一助となるでしょう。
体のコンディションをサポート
マグネシウムは、筋肉や神経の働きの調整だけでなく、日中の活動でこわばった筋肉をゆるめたり、体内のエネルギー産生を支える役割を担っていたりします。
特に筋肉の弛緩を助ける作用は、眠りに入る前の「体がリラックスしていく感覚」と深く関わっていると考えられています。
また、マグネシウムは血流のスムーズさを支える働きにも関与しており、心地よい体温変化を促す点でも役立つといわれています。
これにより副交感神経が優位になり、休息モードに移行しやすくなるのです。
つまり、マグネシウムは「眠りを直接つくる」ものではなく、体全体をリラックスしやすい状態に整えるサポート役といえるでしょう。
安眠を妨げやすい6つの悪習慣

どれだけ寝る前にリラックスしても、日常の習慣が眠りを妨げてしまうことがあります。
特に知らず知らずのうちに続けている行動が、睡眠の質を下げる原因となっている場合も少なくありません。
ここでは、安眠を遠ざけやすい6つの悪習慣を紹介します。
自分の生活に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。
過度な飲酒や喫煙
寝つきをよくするためにお酒を飲む方もいますが、アルコールは一時的に眠気を感じさせる一方で、深い眠りを妨げる原因になるといわれています。
特に夜中に目が覚めやすくなったり、朝起きてもすっきりしない感覚につながったりすることがあり、お酒を飲み過ぎたことがある方の大半がこうした感覚を経験したことがあるはず。
また、飲酒は体内のマグネシウム排出を増やす可能性が指摘されており、栄養バランスの乱れにも影響することが懸念されます。

一方で、喫煙も覚醒作用を持つニコチンが自律神経を刺激し、眠りに入りにくくなる原因になることがあります。
寝る直前の喫煙は特に避けた方が良いとされ、習慣化している方は、少しずつ本数やタイミングを見直すことで睡眠の質の改善につながるでしょう。
まずは「寝酒を習慣にしない」「寝る前の喫煙を控える」といった小さな工夫から始めることから意識してみるのがおすすめです。
カフェインの過剰摂取
カフェインは眠気を和らげて集中力を高める作用があるため、日中のパフォーマンス維持に役立つ一方で、摂り方によっては睡眠に影響を与える可能性があります。
特に夕方以降にコーヒーや紅茶、エナジードリンクを飲むと、体に残ったカフェインが夜の入眠を妨げ、眠りが浅くなる原因になることも。
さらにカフェインは、利尿作用によって夜間のトイレ回数を増やすこともあり、結果として睡眠が分断されやすくなるケースも見られます。
睡眠を優先したい場合は、午後のカフェイン摂取を控えたり、カフェインレスコーヒーやハーブティーなどを取り入れたりすると良いでしょう。
日中の活力と夜の休息、両方を意識してバランスを取ることが大切です。
スマホ依存
就寝前についスマホを眺めてしまうという習慣は、現代人の多くが抱える悩みの一つです。
SNSのチェックや動画視聴は、楽しい一方で脳を刺激し、心を落ち着けにくくする要因になります。
特にブルーライトは体内時計に影響を与えることがあり、夜に浴び続けると「まだ眠る時間ではない」と脳が錯覚し、自然な眠気を妨げてしまう可能性があると指摘されています。
また、他者との情報のやり取りやコメントへの反応は、心を興奮させやすく、布団に入ってからも思考が止まらなくなることがあります。
こうした「脳の覚醒状態」が続くと、入眠が遅れるだけでなく、夜中に目覚めやすくなる可能性も。
眠りを整えたいときは、就寝の30分前にはスマホを手放し、ベッドに持ち込まない習慣を試してみると良いでしょう。
代わりに読書や軽いストレッチなどを取り入れることで、安心感のある「寝る前の儀式」を作ることができます。
運動不足
日中に体をあまり動かさない生活を続けていると、夜になっても体に適度な疲労感が得られず、結果として眠りに入りにくくなるケースがあります。
特にデスクワーク中心で長時間座りっぱなしの生活は、血流の滞りや筋肉のこわばりを招きやすく、休息時のリラックスを妨げる要因になりやすいのです。
とはいえ、無理な運動をする必要はありません。
日常の中でできるだけ階段を使うようにしたり、通勤の一部を歩くようにしたり、夕方に軽くストレッチをしたりなど、体をほどよく動かすだけでもコンディションを整えやすくなります。
また、適度な運動は体温リズムや自律神経の切り替えを整える助けとなり、夜の休息モードへ移行しやすくなるとも考えられています。
大切なのは「毎日少しずつ続けること」。
週末にまとめて運動するよりも、日々の中でこまめに体を動かすよう心掛けることで、安眠しやすい環境作りの支えになるでしょう。
不安や緊張
心配ごとや緊張感が強いと、布団に入っても頭の中で考えごとが止まらず、なかなか眠りに入れないことがあるものです。
不安や悩みは自律神経を刺激し、交感神経が優位になるため、体も心も休息モードに切り替わりにくくなるのです。
こうした状態を和らげるためには、寝る前に「気持ちを整理する時間」を作るのがおすすめです。
たとえば、翌日の予定や不安なことを紙に書き出したり、ゆったりと深呼吸を繰り返したり、軽いストレッチで体をほぐしたりなど。
また、アロマや音楽などを利用して「安心できる空間」を演出するのも、リラックスタイムを上手に演出する代表的な方法の一つです。
不規則な生活リズム
就寝時間や起床時間が日によって大きく異なると、体内時計が乱れやすくなります。
夜更かしや休日の寝だめは一時的には心地よく感じても、その後の眠気やだるさにつながり、結果的に睡眠の質を下げる原因となることが少なくありません。
「ドラマを観ていたら、ついやめどきがわからなくなり、深夜遅くまで観てしまった」
「ゲームに夢中になって夜更かしをしてしまった」
「友達と遅くまで話し込んでしまった」
こんな経験は、きっと誰にでもあるはずです。
たまにはこうして楽しい時間を思い切り満喫してストレスを発散するのも大切ですが、慢性的になると生活リズムが狂ってしまうリスクも。
体内時計は光や食事の時間、活動量といった生活リズムによって調整されています。
そのため、毎日できるだけ同じ時間に起きて朝日を浴び、食事や運動を規則的に行うことが心身のコンディションの安定につながります。
寝る時間を完璧に一定にするのは難しくても、まずは「起きる時間」を固定することから始めてみると良いでしょう。
まとめ│5つのテクニックで良質な睡眠を手に入れよう!

今回は、寝る前に実践できるリラックス法として「音楽を聴く」「アロマを楽しむ」「ストレッチ・ヨガを行う」「入浴でリフレッシュする」「リラックス空間を演出する」の5つ方法をご紹介しました。
いずれも大掛かりな準備などは不要で、生活にすぐ取り入れられるシンプルな方法です。
また、睡眠の質を高めるには、日中の生活リズムや食事の工夫も大切です。
特に、心身の安定やリラックスを支える栄養素として注目されているマグネシウムは、食事や入浴、ボディケアなどさまざまな形で取り入れられるのが魅力。
もちろん効果の感じ方には個人差がありますが、自分に合う方法を選び、無理なく続けることが上手なリラックスタイムの導入と快眠への近道といえるでしょう。
安眠を妨げる習慣を少しずつ見直しながら、手軽なリラックス法や栄養習慣を組み合わせることで、ぐっすりと休める夜をデザインしやすくなります。
ご自分に合った方法を積極的に採用し、快適なライフスタイルの実現を目指しましょう!