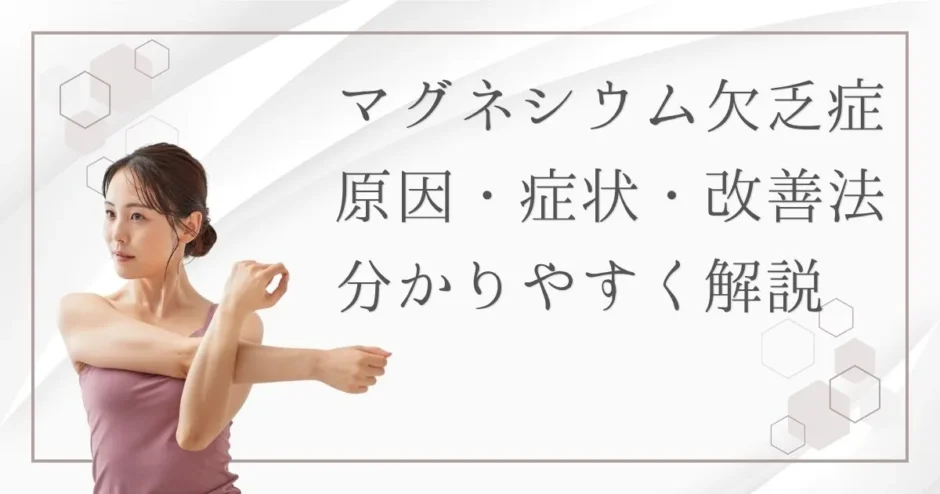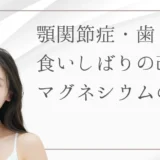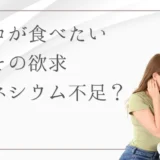現代人の健康を支えるのに欠かせないミネラルの1つである、「マグネシウム」。
マグネシウムは、筋肉の動きや神経の伝達、エネルギー代謝、骨の形成など、体内で800種類以上の酵素反応に関わるといわれています。
ところが、忙しい日常や偏った食生活、ストレスの多い環境では、気付かないうちにマグネシウムが不足しやすく、厚生労働省は消化器系疾患や2型糖尿病、長期のアルコール依存、加齢などを不足リスクとしてあげています。
今回は、マグネシウム欠乏症の原因や症状、改善のための具体的な方法をわかりやすく解説します。
「最近なんとなく体調が優れない…」「健康のために何を意識すればいいか分からない…」という方は、ぜひ参考にしてください。
参照:マグネシウム│厚生労働省
マグネシウム欠乏症とは?

マグネシウム欠乏症とは、体内のマグネシウム量が不足し、筋肉・神経・心臓・代謝などの働きに支障が出る状態を指します。
マグネシウムは、体内でエネルギーを作る力や、ストレスへの抵抗力にも関係しているため、不足するとさまざまな不調が現れます。
ここでは、具体的な症状を詳しく見ていきましょう。
マグネシウム欠乏症の主な症状
マグネシウム欠乏で現れる症状は、大きく「身体的な症状」「精神的な症状」「循環器・代謝への影響」の三つに分けられます。
身体的な症状
マグネシウム不足による代表的な身体症状が、「筋肉のけいれん」や「こむら返り」とされています。
夜間や運動中にふくらはぎがつる経験をしたことがある人は多いでしょう。
マグネシウムが筋肉の収縮と弛緩をコントロールする役割を担っているため、不足するとこうした症状が現れやすくなるといわれています。
また、筋肉のぴくつきやまぶたのけいれん、しびれ、手足の震えなども、神経伝達がうまくいかなくなることで起こる典型的な症状です。
エネルギー代謝が低下すると、慢性的な倦怠感や疲労感、体の重さを感じるようになることも。
さらに、マグネシウムは消化器の働きにも関わっており、不足すると食欲不振や便秘、吐き気などの消化不良を起こすことがあります。
これらの症状は一見、他の原因と見分けがつきにくいですが、複数の不調が重なっている場合は、マグネシウム不足を疑ってみることも大切です。
 マグネシウム不足の症状と招く病気のリスクとは?最新研究が明かす健康への影響と予防法
マグネシウム不足の症状と招く病気のリスクとは?最新研究が明かす健康への影響と予防法
参照:マグネシウム欠乏症│MSDマニュアル プロフェッショナル版
精神的な症状
マグネシウムは「心のミネラル」とも呼ばれるほど、精神の安定に深く関わっています。
マグネシウムが不足すると、神経伝達物質のバランスが崩れやすくなり、ストレスに過敏に反応したり、感情の起伏が激しくなったりすることがあります。
具体的には、イライラや不安感、集中力の低下、気分の落ち込み、睡眠の質の低下などが代表的な症状です。
眠りが浅くなったり、寝つきが悪くなったりするのも、マグネシウム不足によって自律神経の働きが乱れているサインかもしれません。
また、ストレスを受けると体内のマグネシウムが多く消費されるため、精神的な負担が続くほど欠乏が進みやすくなるという悪循環に陥ります。
近年では、マグネシウム不足と不安障害・うつ状態の関連も研究で示唆されており、心の健康を守るうえでも欠かせないミネラルだといえるでしょう。
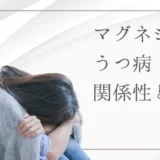 マグネシウムとうつ病の関係とは?精神疾患予防に期待される効果と正しい摂取方法
マグネシウムとうつ病の関係とは?精神疾患予防に期待される効果と正しい摂取方法
循環器・代謝への影響
心臓の筋肉(心筋)の収縮やリズムを整える働きにもマグネシウムが関与しているため、欠乏すると動悸や不整脈などのリスクにつながることがあります。
また、マグネシウムには血管をしなやかに保つ作用もあるため、不足すると血管が収縮しやすくなり、高血圧や頭痛を引き起こす要因となることも。
代謝の面では、マグネシウムがインスリンの働きをサポートしているため、長期的な不足は血糖コントロールを乱し、糖尿病のリスクを高める可能性があります。
さらに、カルシウムやカリウムとのバランスが崩れると、細胞内外のミネラルバランスが乱れ、疲労感や冷えなどにつながる場合もあります。
このように、マグネシウムは体の根幹に関わる循環や代謝の機能を支える存在です。目立った症状がなくても、長期間の不足は少しずつ体に負担をかけていくため、日常的に意識しながら、できるだけ積極的に摂取するよう心掛けることが大切です。
 マグネシウムで血圧は下がる?上がる?経皮吸収での効果とおすすめの使用方法も紹介
マグネシウムで血圧は下がる?上がる?経皮吸収での効果とおすすめの使用方法も紹介
低マグネシウム血症とは?
マグネシウムの欠乏が慢性的あるいは深刻化すると、低マグネシウム血症のリスクが高まります。
低マグネシウム血症とは、血液中のマグネシウム濃度が正常範囲(おおよそ1.8〜2.6mg/dL)を下回る状態を指します。
単なる一時的なマグネシウム不足とは異なり、体内のバランスが大きく崩れているサインであり、注意が必要です。
この状態は、マグネシウムの摂取不足だけでなく、腸からの吸収障害や腎臓からの過剰排出、または特定の薬(利尿薬や抗生物質など)の影響によって引き起こされることがあります。
特に高齢者や糖尿病、消化器疾患を持つ人では起こりやすい傾向があります。
症状としては、筋肉のけいれん、しびれ、吐き気、脱力感などのほか、重度の場合には不整脈やけいれん発作、意識障害などを伴うことも。これらは命に関わるケースもあるため、放置は禁物です。
血液検査で低マグネシウム血症が確認された場合は、医師の指導のもとで点滴や内服などによる治療が行われます。自己判断でのサプリ摂取では改善が難しいことも多く、正確な診断と適切な治療が重要です。
マグネシウム欠乏の主な原因

マグネシウムが不足する原因は、単に食事量の問題だけではありません。
現代人の生活習慣や環境要因、ストレス、睡眠、飲酒など、日常のさまざまな行動が関係しています。
ここでは、マグネシウム欠乏を引き起こす主な要因を具体的に見ていきましょう。
環境による原因
日本では、地理的・環境的な要因からマグネシウムが不足しやすいといわれています。
その大きな理由の1つが「土壌と水質」です。
日本の土壌は酸性寄りで、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルが溶け出しやすく、作物に十分な量が含まれにくい傾向があります。
さらに、水質も影響しています。
日本の水道水は「軟水」が一般的で、マグネシウムやカルシウムといったミネラルの含有量が少ないのが特徴です。
これに対し、欧米諸国の多くでは「硬水」が主流で、水から自然にミネラルを摂取できる環境が整っています。
つまり、日本では「食事以外からミネラルを取り入れる機会が少ない」という構造的な問題があるため、意識的にマグネシウムを補う必要があるのです。
ストレスの多い生活
精神的なプレッシャーや緊張、慢性的な疲労などが続くと、体はストレスホルモン(コルチゾールやアドレナリンなど)を分泌します。
このとき、神経や筋肉の興奮を抑えるためにマグネシウムが大量に使われ、血中濃度が低下します。
さらに、強いストレス下では交感神経が優位になり、尿中へのマグネシウム排出量も増加。
つまり、ストレスがかかるほど、マグネシウムを「使いながら失う」状態に陥りやすくなるのです。
この状態が長期間続くと、ストレス耐性が落ちてさらに疲れやすくなる、イライラしやすくなるといった悪循環が生まれやすくなります。
ストレスの多い現代社会では、意識的なリラックス習慣や十分な休息をとることも、心身の健康を守るために重要なセルフケアといえるでしょう。
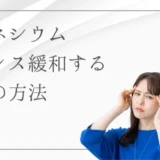 マグネシウム不足でストレスが悪化?心と体を整える現代的栄養戦略
マグネシウム不足でストレスが悪化?心と体を整える現代的栄養戦略
睡眠不足や不規則な生活
私たちの体は、眠っている間にホルモン分泌や自律神経のバランスを整え、体内のミネラルを再利用・調整しています。
しかし、夜更かしや短時間睡眠が続くと、この回復サイクルが乱れ、マグネシウムの吸収や保持がうまく働かなくなる場合があります。
さらに、マグネシウムは睡眠ホルモン「メラトニン」の生成をサポートする働きがあるため、不足すると寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりしやすくなる可能性も。
結果として、睡眠の質が下がり、疲労が取れにくくなるという悪循環に陥りやすくなるのです。
不規則な食事や夜型の生活リズムも、体内時計やホルモン分泌のリズムを乱し、マグネシウムの代謝を阻害します。
健康的なマグネシウムバランスを保つために、十分な睡眠時間の確保と、できるだけ一定の生活リズムを心掛けましょう。
 マグネシウムが睡眠の質を左右する?不足の原因と改善方法を徹底解説!
マグネシウムが睡眠の質を左右する?不足の原因と改善方法を徹底解説!
過度なダイエットや偏食
極端な食事制限をすると、栄養バランスが崩れるリスクが高まりやすくなります。
特に「糖質オフ」「野菜抜き」などの偏ったダイエットでは、ビタミンやミネラルの吸収を助ける栄養素まで不足してしまうことも。
また、カロリーを気にして食事量そのものを減らすことも、マグネシウムをはじめとする各種栄養素の摂取量の減少につながります。
さらに、インスタント食品や加工食品に頼った食生活にも注意が必要です。
これらの食品は製造過程でミネラルが失われているものが多いことに加え、リン酸塩などの添加物がマグネシウムの吸収を妨げることもあります。
健康的に体を整えるには、摂取量を減らすことよりも「栄養バランスを整えること」が大切です。過度な制限ではなく、自然な食材から必要なミネラルをしっかり補う意識を持ちましょう。
 マグネシウムで痩せるって本当!?ダイエットに役立つ科学的な6つの理由と5つの実践法
マグネシウムで痩せるって本当!?ダイエットに役立つ科学的な6つの理由と5つの実践法
アルコールやカフェインの過剰摂取
アルコールやカフェインには強い利尿作用があるため、摂取後に尿とともにマグネシウムが排出されやすくなります。
特に、毎晩の飲酒やコーヒーを何杯も飲む習慣がある人は、知らないうちに体内のマグネシウムが減少していることがあるかもしれません。
アルコールを多く摂ると、肝臓での代謝過程でもマグネシウムが消費されます。
さらに、アルコールが腸の粘膜を刺激して栄養吸収を妨げるため、食事からのマグネシウム吸収効率も低下気味に。
これが慢性的に続くと、疲労感や筋肉のけいれん、イライラといった症状が現れやすくなるとされています。
一方、カフェインはコーヒーだけでなく、紅茶、緑茶、エナジードリンクなどにも含まれており、知らないうちに摂取量が増えがちです。
カフェインを摂りすぎると交感神経が刺激され、ストレスホルモンが分泌されるため、マグネシウムの消耗をいっそう促進します。
アルコールやカフェインを完全に断つ必要はありませんが、栄養面では「飲みすぎない」「水をしっかりとる」「食事でマグネシウムを補う」といった意識が大切です。
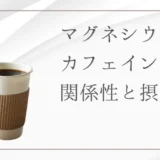 コーヒー(カフェイン)はマグネシウムの吸収を阻害する?健康効果と関係性
コーヒー(カフェイン)はマグネシウムの吸収を阻害する?健康効果と関係性
運動不足または過剰な運動
マグネシウムのバランスは運動量とも深く関係しており、運動不足と過剰な運動、どちらもマグネシウム欠乏を招く可能性があります。
運動不足の場合、筋肉への血流や代謝活動が低下し、細胞内でのマグネシウムの利用が滞ります。
筋肉量が減ると、体に蓄えられるマグネシウム量そのものも減少し、エネルギー代謝が落ちやすくなるのです。
これにより、少し動いただけで疲れやすくなったり、体の冷えやだるさを感じたりすることがあります。
一方、過剰な運動もマグネシウムを大量に消耗させる場合があるので注意が必要です。
汗とともにミネラルが排出される上、筋肉の収縮・修復にもマグネシウムが必要なため、激しいトレーニングを続ける人は慢性的な不足に陥りやすい傾向があります。
特に夏場やサウナ利用後など、大量の汗をかいたときは注意が必要です。
健康維持のためには、ウォーキングやストレッチ、軽い筋トレなどの適度な運動が理想です。
健康・ウェルネスの分野ではあまり語られませんが、「薬の影響によるマグネシウム欠乏」は見過ごせない重要なテーマです。
実際、さまざまな薬剤が体内のマグネシウムレベルを低下させることが知られています。医師の中にはこの点を十分に理解している方もいますが、依然として認識が行き届いていないケースも少なくありません。
科学的にマグネシウム不足を引き起こすことが確認されている薬剤には、以下のようなものがあります。
- 抗生物質
- コレステロール低下薬
- 下剤
- 副腎皮質ステロイド
- 抗がん剤
- 降圧剤
- インスリン
- 抗ウイルス薬
- プロトンポンプ阻害薬(PPI)
これらの薬は、それぞれ異なる作用機序でマグネシウムの吸収や排泄に影響を及ぼします。
たとえば、PPIは胃酸の分泌を抑える一方で、マグネシウムの腸内吸収を妨げることが知られています。
また、利尿作用を持つ降圧剤や下剤の長期使用は、尿や便を通じてマグネシウムを過剰に排出させてしまうことがあります。
そのため、これらの薬を使用している人で、筋肉のけいれん、こむら返り、倦怠感、動悸などの症状が見られる場合は、医師に相談し、マグネシウム値の測定を依頼することが大切です。
必ずしも薬を中止する必要はありませんが、マグネシウムの補給や薬剤の調整によって、症状の改善が期待できるケースもあります。
参照:マグネシウム│厚生労働省
マグネシウム不足を放置するとどうなる?

まず、循環器系では心筋の収縮や血管の拡張に異常が生じ、不整脈や高血圧、動脈硬化のリスクが高まる可能性が示唆されており、低マグネシウム状態が続くと、心疾患や脳卒中の発症率が上昇するという報告もあります。
また、マグネシウムはインスリンの働きを助け、血糖値を安定させる役割を持つため、不足すると糖尿病やメタボリックシンドロームのリスクが増加するとされています。
代謝の不調は肥満や脂質異常症にもつながりやすく、生活習慣病の温床となりやすいのです。
骨や歯の健康にも関係があり、カルシウムの代謝が乱れることで、骨密度低下に関与する可能性が指摘されています。特に女性や高齢者は注意が必要です。
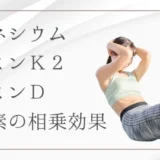 骨の健康をサポートする黄金トリオ!マグネシウム×ビタミンK2(メナキノン)×ビタミンD
骨の健康をサポートする黄金トリオ!マグネシウム×ビタミンK2(メナキノン)×ビタミンD
さらに精神面への影響も、「精神的な症状」で先述した通りです。
このように、マグネシウム不足は体と心の両面に影響を及ぼし、放置すれば生活習慣病やメンタル不調へと進行していく危険性があります。
気になる症状がある人は、早めに生活習慣を見直すとともに、「マグネシウム不足診断」などでセルフチェックを行うのもおすすめです。

マグネシウムを補う方法

マグネシウムは体内で生成できないため、日々の生活の中で意識的に補うことが大切です。
ここでは、代表的なマグネシウム補給の方法をご紹介します。
食事でマグネシウムを補う
マグネシウムを補う上でもっとも基本的なのが、毎日の食事から自然に摂取する方法です。
マグネシウムは、さまざまな食品に含まれていますが、特に多いのは豆類・海藻類・ナッツ類・魚介類・全粒穀物などです。
たとえば、納豆、ひじき、アーモンド、あさり、玄米などは、手軽にマグネシウムを摂れる代表的な食材といえるでしょう。
白米を玄米や雑穀米に変えたり、間食にナッツを取り入れたりするだけでも、マグネシウム摂取量を無理なく増やすことができます。
また、ビタミンB6やビタミンDを一緒に摂るとマグネシウムの吸収が高まるため、魚や卵、緑黄色野菜などを組み合わせた食事が理想的です。
日々の食事で少しずつ意識するだけでも、体のバランスは大きく変わります。健康維持のために、まずは「自然な食材からマグネシウムを取り入れる」ことから始めてみましょう。
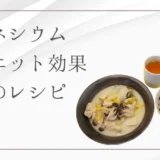 【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選
【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選
サプリでマグネシウムを補う
食事で十分なマグネシウムを摂れない場合や、忙しくて食生活が偏りがちな人には、サプリメントによる補給も有効な手段です。
サプリなら吸収率や配合量を調整しやすく、継続的に摂取できるという利点があります。
マグネシウムを摂取できる代表的なサプリには、酸化マグネシウム、クエン酸マグネシウム、グリシン酸マグネシウムなどがあります。
酸化マグネシウムは含有量が多くコストも低いですが、吸収率は比較的低め。
一方、クエン酸やグリシン酸タイプは体に吸収されやすく、胃腸への刺激が少ないのが特徴です。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、成人男性で1日約360mg、女性で約290mgがマグネシウムの推奨摂取量とされています。
サプリを利用する場合も、これを目安に過剰摂取にならないよう気をつけましょう。
特に、1,000mgを超えるような摂取は下痢や吐き気を起こすことがあるため注意が必要です。
また、腎臓病や心疾患のある方、利尿薬を使用している方は、マグネシウム排泄や体内バランスが変化しやすいため、自己判断での摂取は避け、医師または薬剤師に相談することが大切です。
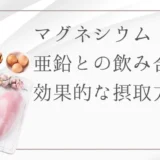 マグネシウムと亜鉛は一緒に摂っていい?飲み合わせの効果と摂取のコツを解説
マグネシウムと亜鉛は一緒に摂っていい?飲み合わせの効果と摂取のコツを解説
参考:日本人の食事摂取基準(2025年版)の策定ポイント│厚生労働省
入浴剤でマグネシウムを補う
マグネシウムを補う方法の中でも、最近注目されているのが「入浴によるケア」です。
特に、エプソムソルト(硫酸マグネシウム)を使った入浴は、手軽にマグネシウムを取り入れながら、リラックスタイムを楽しめる方法で、欧米では一般的です。
エプソムソルトを活用した入浴は、体の芯から温まりやすく、冷えや疲労感がある人、肩こりや筋肉のこわばりが気になる人にも気軽に取り入れやすい方法といえるでしょう。
また、リラックス効果が高いため、ストレス緩和や睡眠の質を整えるサポートにもつながります。
ただし、マグネシウム入浴剤の効果は医薬品のようなものではなく、あくまで健康・美容のサポートを目的としたものです。肌が敏感な人は、まず少量から試し、自分の体質に合うかを確認しましょう。
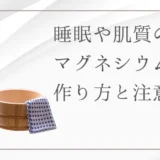 マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法
マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法
クリームでマグネシウムを補う
マグネシウムクリームやバーム、スプレーなどの外用ケアも人気です。
マグネシウムクリームは、肩こりや腰の張り、脚のだるさなど、特定の部位にピンポイントで使えるのが魅力。
運動後のケアやデスクワークで凝りがちな部分に塗ることで、マッサージを兼ねながら血行を促進できるのがメリットです。
スプレータイプであれば広範囲に使いやすく、バームは保湿力が高いため、乾燥しやすい季節にも向いています。
ただし、外用タイプのマグネシウムは体内濃度を直接上げることを目的とするものではなく、あくまでリラクゼーションや筋肉ケアをサポートするアイテムです。
敏感肌の方やアトピー体質の方は、刺激を感じることがあるため、必ず少量から試すようにしましょう。
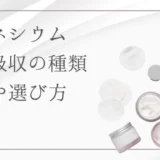 マグネシムバーム・クリーム・スプレーの違いとは?目的別おすすめの使い方を解説
マグネシムバーム・クリーム・スプレーの違いとは?目的別おすすめの使い方を解説
まとめ|マグネシウム欠乏症を理解して意識的に栄養を摂取しよう

マグネシウム欠乏症は、現代人にとって決して他人事ではありません。
食生活の変化やストレス、睡眠不足、過労などが重なり、知らないうちにマグネシウムが不足している人は多いはずです。
軽い筋肉のけいれんや疲労感、イライラ、不眠などを感じている方は、体からの小さなSOSサインをしっかりキャッチし、今日からでもライフスタイルを見直すのがおすすめです。
マグネシウムを補うために、まずは豆類・海藻・ナッツ類・全粒穀物など、自然な食材からの摂取を心掛けましょう。
それでも不足を感じる場合は、サプリメントやマグネシウム入浴、外用ケアなどを併用し、無理なく取り入れるのも有用な選択肢です。
心と体は密接に結びついています。
マグネシウムを十分に補うことは、単なる栄養補給にとどまらず、ストレスに強く、穏やかで安定した日々を過ごすための基盤作りにもつながります。
日々の工夫を積み重ねながら、体の内側から心身を整えていきましょう!