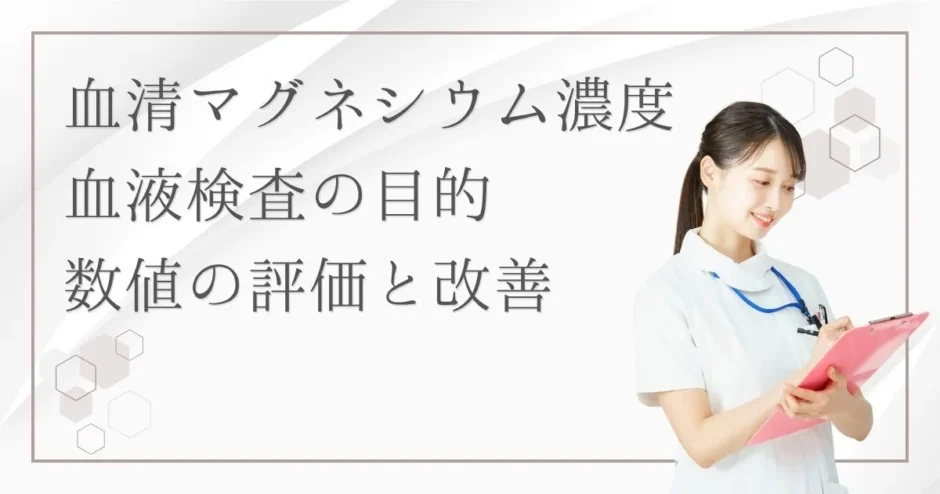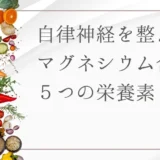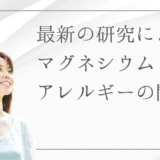日ごろから「マグネシウム」を意識することは少ないかもしれません。
しかしマグネシウムは、臨床検査における生化学的検査(電解質検査)の項目にあげられるように、私たちの体に欠かせない物質で、エネルギーの産生や筋肉の動き、神経の働き、心臓のリズムの維持など、生命を支える800種類もの酵素反応に関わる欠かせないミネラルです。
それにも関わらず、現代の食生活やストレス環境の中で、知らないうちにマグネシウムが不足してしまうケースが少なくありません。
今回は、マグネシウムを血液検査で測る目的や、数値が高い・低いときに考えられること、検査を受ける流れや注意点までをわかりやすく解説します。
自分の体のミネラルバランスを知ることは、健康を守る第一歩です。
ぜひ本記事を通じて、マグネシウムと上手に付き合うヒントを見つけてください。
マグネシウム検査の目的とは?

マグネシウム検査は、体内のミネラルバランスを確認するために行われる大切な検査で、血液中のマグネシウム濃度を測定することで、体の状態や潜在的な不調のサインを早期に見つける手がかりになります。
では、具体的にどのような目的で検査が行われるのでしょうか。
はじめに、マグネシウム検査の目的や、検査の流れについて解説します。
マグネシウム検査の主な目的
マグネシウム検査の主な目的は、体内のマグネシウム量を把握し、健康状態をより正確に評価することです。
マグネシウムは、筋肉や神経、心臓、骨、代謝などに深く関わる重要なミネラルであり、そのバランスが崩れると多様な不調を引き起こす可能性があります。
血液検査では、血清マグネシウム濃度(血液中のマグネシウムの濃度)を測定し、異常を発見して原因の特定や治療方針の決定に役立てるのが一般的です。
特に糖尿病や腎臓疾患、心疾患などの持病がある人は、マグネシウムの値を定期的に確認することで、病状の進行を予防したり、薬の影響を評価したりする指標になります。
つまりマグネシウム検査は、単なる数値の確認だけでなく、「今の体がどれだけスムーズに働いているか」を知る重要な健康チェックといえます。
どんなときにマグネシウム検査を受けるのか?
マグネシウム検査は、特定の症状が現れたときや、持病・薬の影響でマグネシウムのバランスが崩れやすいと考えられるときに行うのが普通です。
もちろん、医療機関で自主的に検査を受けることができます。
たとえば、筋肉のけいれんやこむら返り、手足のしびれ、動悸、倦怠感、不眠、便秘などが続くなど、体内のマグネシウム不足が疑われる場合。また、逆に吐き気や血圧の低下、反射の鈍化などが見られるときは、マグネシウムが過剰になっている可能性もあります。
さらに、糖尿病や腎臓疾患、消化器のトラブル(下痢・嘔吐など)がある人、利尿剤や抗生物質などの薬を服用している人は、体内のマグネシウム量が変動しやすいため、定期的な検査が推奨されるのが一般的です。
健康診断では通常、血清マグネシウムの測定は含まれていませんが、医師の判断で追加検査として行われることもあります。
体調不良が続くときや、慢性的な疲れを感じるときは、一度マグネシウム検査を検討してみると良いでしょう。
マグネシウム検査の流れ
一般的なマグネシウム検査の流れは、次のとおりです。
- 医療機関で医師の問診を受け、症状や既往歴、服薬状況などを確認する
- 必要に応じて採血し、血液検査を実施する
- 通常1〜3日程度で結果が報告され、医師から異常の有無の説明を受ける
このとおり、マグネシウム検査は一般的な血液検査の一項目として行われるシンプルな検査なので、特別な機器や長時間の検査を必要としません。
採血から結果が出るまでの流れも比較的スムーズです。
採血自体は数分で終わり、検査機関に送られた血液は分析装置でマグネシウム濃度が測定されます。
マグネシウム値の変化は単独で判断するのではなく、カルシウムやカリウムなど他の電解質とのバランスも考慮して評価されます。そのため、血液検査全体の結果を総合的に見ることが大切です。
マグネシウム検査を受けるための準備方法
マグネシウム検査は、基本的に特別な準備を必要としない検査ですが、検査前の行動や食事によって結果が変動することがあるため、事前に確認しておくことが大切です。
まず、検査前の食事について、マグネシウムは食品中に多く含まれるため、検査前に摂取した食べ物の影響を避けるために、医療機関によっては「前日の夜から絶食」や「当日は朝食を抜く」といった指示が出される場合があります。
特に健康診断などで他の血液検査と同時に行う場合は、指示に従うことが重要です。
また、サプリメントを摂取している場合は、検査前に必ず医師に申告しましょう。
マグネシウムやカルシウム、ビタミンDなどのサプリメントは、血中濃度に影響を与える可能性があります。
さらに、検査直前の激しい運動やアルコール摂取も避けた方が無難でしょう。
これらの行動は一時的にマグネシウムの代謝を変化させ、正確な結果を得にくくすることがあるためです。
特別な準備は不要ですが、検査前は普段より刺激の少ない生活を意識すると安定した結果につながります。
血中マグネシウムの正常値

血液中のマグネシウム濃度は、どのくらいの数値が正常値といえるのか、検査を受ける誰しもが気になるところでしょう。
ここでは、血中マグネシウムの正常値と、その数値が示す意味について見ていきましょう。
マグネシウム濃度の正常値
血液中のマグネシウム濃度(血清マグネシウム値)の正常範囲は、おおよそ1.8〜2.6mg/dL(0.75〜1.10mmol/L)とされています。
この範囲にある場合、体内のマグネシウムバランスはおおむね良好と考えられます。
マグネシウムは体内に約25gほど存在し、その約60%が骨に、残りが筋肉や神経、細胞内液などに分布しており、血液中のマグネシウムは全体のわずか1%程度にすぎません。
しかし、神経の伝達、心臓の拍動、筋肉の収縮、エネルギーの産生など、生命活動に欠かせない重要な役割を果たしています。
ただし、血清マグネシウム濃度が正常範囲にあっても、細胞内や骨のマグネシウムが不足している場合もあります。
そのため、検査結果だけで安心せず、症状や生活習慣、服薬状況などもあわせて医師が総合的に評価することが大切です。
参考:マグネシウム濃度の異常の概要│MSDマニュアル プロフェッショナル版
一般的に、血清マグネシウム検査は体全体のマグネシウム状態を正確に反映する検査とはいえません。
というのも、体内のマグネシウムのうち血清に存在するのはわずか約1%で、残りのほとんどは筋肉や骨などの組織に分布しているからです。
そのため、血液検査で「正常」と判定されても、体全体で見ればマグネシウムが不足している可能性はあります。
心臓の正常な働きを維持するために、体は血清マグネシウム濃度を一定に保とうとする仕組みをもつため、筋肉や骨のマグネシウムを消費してでも血中濃度を維持しようとするのです。
したがって、血液の値が正常でも、組織内では不足が進んでいることが少なくありません。
このような背景から、筋肉のけいれんや倦怠感、不眠といった症状のほうが、体内のマグネシウム状態をより正確に示すサインと考えられています。
実際、血清マグネシウム検査は一般的な健康診断ではほとんど行われず、重症患者が入院している集中治療室(ICU)など、限られた状況でのみ実施されるのが一般的です。
マグネシウム不足の診断は、多くの場合「経過観察によって判断される」ことが多いのが現実です。
たとえば、医師がマグネシウム不足を疑い、血液検査の値が正常でも3か月ほどマグネシウム補給を試みた結果、症状が改善すれば「やはり不足していた」と判断されるという流れです。
世界的にも、血液検査では正常範囲にあっても、実際には慢性的なマグネシウム不足に陥っている人が多いと報告されています。
マグネシウム値が低いとどうなる?
マグネシウム値が低い状態は「低マグネシウム血症」と呼ばれ、体のさまざまな機能に影響を及ぼします。
たとえば、マグネシウムは神経や筋肉の興奮を抑える働きもあるため、不足すると神経伝達が過敏になり、筋肉のけいれんやこむら返り、手足のしびれなどが起こりやすくなるとされています。
また、マグネシウムはカルシウムやカリウムと密接に関わっており、不足するとこれらのミネラルのバランスが崩れやすく可能性も。その結果、心臓のリズムが乱れやすくなったり、動悸や息切れ、血圧の上昇などの症状が現れたりする場合があるのです。
さらに、マグネシウム不足はエネルギー産生にも影響するため、慢性的な疲労感や集中力の低下、睡眠の質の悪化など、心身のパフォーマンス低下を感じやすくなる可能性もあります。
精神面でも、イライラしやすくなったり、不安感が強くなるケースが少なくありません。
低マグネシウム血症の原因として、偏った食事、アルコールの過剰摂取、下痢や嘔吐による排出増加、利尿剤の使用、糖尿病による尿中排泄の増加などがあげられます。
軽度の不足は食事改善で補えますが、重度の場合は医師による点滴やサプリメント管理などで工夫する必要があります。
マグネシウム不足による主なリスク
| 種類 | 主なリスク | 対策 |
|---|---|---|
| 筋肉・神経系 | こむら返り、手足のしびれ、筋肉のけいれん、動悸 | マグネシウムを含む食品(海藻類、ナッツ、豆類、魚介)を積極的に摂取し、過度なカフェイン・アルコールを控える |
| 心血管系 | 高血圧、不整脈、動脈硬化の進行リスク | 塩分を控え、バランスの取れた食事と水分補給を心がける。定期的に血圧・心電図のチェックを行う |
| 精神・神経系 | イライラ、不安感、不眠、集中力の低下 | 睡眠環境を整え、深呼吸や軽いストレッチでリラックス。ストレス対策の一助にも |
| 代謝・内分泌系 | インスリン抵抗性の上昇、糖尿病リスク増加 | 野菜・雑穀を中心にした低GI食(※)を意識し、過剰な糖分摂取を控える |
| 骨・関節系 | 骨粗しょう症、筋力低下 | カルシウム・ビタミンD・マグネシウムをバランス良く摂取する(魚、豆腐、緑黄色野菜など) |
| 消化・排泄系 | 便秘、食欲不振、吐き気 | 十分な水分と食物繊維を摂り、腸内環境を整える。発酵食品やぬか漬けなどもおすすめ |
| 全身疲労 | 倦怠感、エネルギー不足、免疫力低下 | 睡眠を確保し、過労を避ける。適度な運動と休養で体力を回復させる |
※低GI食とは、食後の血糖値の上昇をゆるやかにする食事法のことです。玄米や豆類、野菜などGI値の低い食品を選ぶことで、糖の吸収が穏やかになり、血糖コントロールや体への負担軽減に役立ちます。
なお、GI(グリセミック・インデックス)とは、食べた後に血糖値がどの程度上がるかを示す指標で、数値が低いほど血糖値の上昇がゆるやかになります。
 マグネシウム不足の症状と招く病気のリスクとは?最新研究が明かす健康への影響と予防法
マグネシウム不足の症状と招く病気のリスクとは?最新研究が明かす健康への影響と予防法
この表からわかるように、マグネシウム不足は1つの臓器だけでなく、全身の機能に広く影響します。
特にストレスや不規則な生活が続くと消耗しやすいため、日常的に意識して補うのがポイントです。
マグネシウム不足が気になる方は、医師監修の「マグネシウム不足セルフチェック」でチェックしてみましょう。

マグネシウム値が高いとどうなる?
マグネシウム値が高い状態は「高マグネシウム血症(血清マグネシウム濃度が2.6mg/dL(1.05mmol/L)以上)」と呼ばれ、通常は腎臓の機能が低下している場合や、サプリメント・薬剤を過剰に摂取した場合に起こりやすいとされています。
健康な人の場合、腎臓が余分なマグネシウムを尿として排出するため、高マグネシウム血症になることはまれです。
高マグネシウム血症になると、初期には吐き気や眠気、倦怠感、顔のほてりなどの軽い症状が現れます。
進行すると、血圧の低下、脈の乱れ、筋力低下、反射の鈍化などが起こり、重度の場合は意識障害や呼吸抑制に至ることも。
特に腎疾患のある人や高齢者は、体内にマグネシウムが蓄積しやすいため注意が必要です。
原因としては、腎機能の低下に加え、制酸薬(胃薬)や下剤に含まれるマグネシウムを長期間使用しているケースが多く見られます。
高マグネシウム血症を対策するには、医師の指導のもとで薬の種類や摂取量を見直すことが大切です。
また、サプリメントを自己判断で過剰に摂ることも避けましょう。
高マグネシウム血症の主な原因、症状、対策
| 項目 | 主な内容 | 対策・注意点 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 腎機能の低下、マグネシウムを含む制酸薬や下剤の長期使用、サプリメントの過剰摂取 | 腎臓病の有無や服薬状況を医師に伝える。自己判断でのサプリ摂取を控える |
| 初期症状 | 吐き気、倦怠感、眠気、顔のほてり | 症状が続く場合は速やかに受診する |
| 進行症状 | 低血圧、徐脈(脈が遅い)、筋力低下、反射の鈍化 | 医療機関で血液検査と心電図を受け、原因を特定する |
| 重度症状 | 意識障害、呼吸抑制、心停止(まれ) | 緊急時は直ちに医療機関へ。透析や点滴で調整が行われる場合もある |
| 予防のポイント | 腎臓に負担をかけない生活を意識する。薬やサプリの成分を確認し、必要以上の摂取を避ける | 水分をしっかり摂り、定期的な健康診断で腎機能をチェック |
マグネシウムは、適量であれば健康を支える重要なミネラルですが、体外に排出しにくくなるとバランスを崩しやすくなります。
特に腎臓の状態に不安がある方や複数の薬を服用している方は、定期的な検査で数値を確認しておくと安心です。
また、血液検査で高値が出た場合は、自己判断で対応せず、腎臓や薬の影響を含めて医師に相談しましょう。
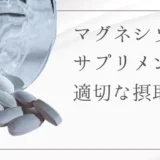 マグネシウムを摂りすぎるとどうなる?よくある症状と適量の目安
マグネシウムを摂りすぎるとどうなる?よくある症状と適量の目安
参考:高マグネシウム血症│MSDマニュアル プロフェッショナル版
マグネシウムの体内での役割
マグネシウムは、体の中で800種類以上の酵素反応を助ける「補酵素」として働く、生命維持に欠かせないミネラルです。
見た目にはわかりにくいものの、私たちの健康の土台を支える“縁の下の力持ち”のような存在です。
マグネシウムの役割でまず注目したいのが、エネルギー代謝への関与でしょう。
マグネシウムは、ATP(アデノシン三リン酸)という体のエネルギー源を活性化させるために不可欠で、細胞が正常に働くための燃料づくりをサポートします。
これが不足すると、疲労感や集中力の低下などにつながることも。
ATPについては、「疲れが取れないのはマグネシウム不足?症状と疲労回復のための3つの摂取法」で詳しく解説しています。こちらも併せてご覧ください。
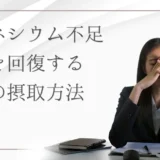 疲れが取れないのはマグネシウム不足?症状と疲労回復のための3つの摂取法
疲れが取れないのはマグネシウム不足?症状と疲労回復のための3つの摂取法
さて、カルシウムが筋肉を収縮させるのに対し、マグネシウムは弛緩(ゆるめる)役として働きます。このバランスが崩れると、こむら返りや筋肉のけいれんなどの身体的な異常だけでなく、メンタル面の不調も起こりやすくなるとされています。
さらに、マグネシウムとカルシウムのバランスは、心臓の働きや血圧の安定、骨の形成、血糖コントロール、ストレス緩和などにも関与しています。つまり、マグネシウムが体内に十分にあることで、体は落ち着いたリズムを保ち、精神的にも安定しやすくなるのです。
「筋肉」「神経」「心臓」「骨」「代謝」など、全身の健康を支える基本ミネラルとして、マグネシウムは私たちの体に欠かせない栄養素なのです。
 マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説
マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説
血液検査結果の見方と注意点

血液検査でマグネシウムの数値を確認する際には、「結果をそのまま鵜呑みにしない」ことが大切です。
なぜなら、数値が正常範囲にあっても、体のどこかでマグネシウムが不足している場合があるからです。つまり、たとえ数値が正常であったとしても安心しないことが大切です。
まず、血清マグネシウム濃度は1.8〜2.6mg/dLが基準範囲とされていますが、この数値は血液中のマグネシウムのみを示しています。
実際には、体内のマグネシウムの大半が骨や筋肉、細胞内に存在しており、血液中は全体のわずか1%ほどです。
そのため、血液検査だけでは「細胞内マグネシウムの欠乏」までは正確にわからないことがあります。
また、検査値は採血時の体調や水分バランス、服薬の影響などでも変動する場合があることも留意しておきましょう。
たとえば、利尿剤や抗生物質、制酸薬などは、マグネシウムの排出量に影響を与えることが知られています。
検査前にこれらの薬を服用している場合は、医師に必ず伝えておくことが重要です。
さらに、マグネシウムはカルシウムやカリウム、ナトリウムなどの他の電解質とのバランスによって働きが変わるため、単独での評価ではなく、これらの数値とあわせて見る必要があります。
もし検査結果に異常が見られた場合でも、すぐに不安になる必要はありません。
医師は、症状・既往歴・生活習慣などを総合的に判断した上で、再検査や食事・生活改善、必要に応じて点滴やサプリメントなどの対応を提案します。
血液検査の結果は、あくまで「体の今の状態を知るための手がかり」なのです。
マグネシウムが不足する主な原因

マグネシウム不足は、現代の生活習慣の中で非常に起こりやすいミネラル欠乏の1つです。
食生活の乱れやストレス、薬の影響、持病など、さまざまな要因が重なって体内のマグネシウム量を減らしてしまうことがあります。
もっとも多いのが、偏った食事によるマグネシウム不足といわれています。
インスタント食品や外食中心の生活では、精製された白米・パン・砂糖などの「精製炭水化物」が多くなり、マグネシウムが豊富な穀物の胚芽や野菜、豆類、海藻などを摂る機会が減ります。
これにより、慢性的に摂取量が不足しがちになります。
次に大きな要因となるのが、ストレスです。
心理的・身体的ストレスがかかると、副腎からストレスホルモン(コルチゾールなど)が分泌されます。
このとき体はマグネシウムを大量に消費し、神経や筋肉の緊張をやわらげようとします。
つまり、ストレスが長引くほど体内のマグネシウムが減りやすくなるのです。
また、アルコールの過剰摂取もマグネシウム不足の大きな原因です。
アルコールは利尿作用を促し、マグネシウムを尿中に排出してしまいます。さらに、飲酒によって腸の吸収機能が低下するため、摂取しても体に吸収されにくくなります。
加えて、慢性疾患や服薬による影響も見逃せません。
たとえば、糖尿病では尿中にマグネシウムが排出されやすく、下痢や嘔吐などの消化器症状が続くと体外に失われやすくなります。
また、利尿剤・抗生物質・制酸薬など一部の薬も、長期使用でマグネシウム濃度を低下させることがあります。
このように、マグネシウム不足は「食生活・ストレス・薬・持病」のどれか1つではなく、複数の要因が重なって起こることが多いものです。
疲れやすい、筋肉がつりやすい、眠りが浅いなどのサインを感じたら、マグネシウムの不足を疑い、生活全体を見直してみることが大切です。
マグネシウム不足セルフチェックでは、ほんの1分程度でご自分のマグネシウムの状態をセルフチェックできます。「マグネシウム、足りているかな?」と疑問をお持ちの方は、ぜひセルフチェックしてみてください。

マグネシウム不足を改善する7つの方法

マグネシウム不足を改善するには、日常生活の中で「摂る・整える・休む」の3つのバランスを意識することが大切です。
食事だけでなく、水分補給や睡眠、ストレス管理など、生活全体を見直すことで自然にマグネシウムの働きを取り戻すことができます。
ここからは、今日から実践できる7つの改善方法を紹介します。
食生活を見直す
マグネシウムは、穀物の胚芽、豆類、ナッツ、海藻、魚、野菜など、自然に近い形の食品に多く含まれています。
一方、白米や白いパン、砂糖などの精製食品を中心とした食事では、マグネシウムの摂取量が大幅に減ってしまいやすくなります。
意識したいのは、「まごわやさしい」食材を取り入れることです。
- ま=まめ
- ご=ごま
- わ=わかめ
- や=野菜
- さ=魚
- し=しいたけ(きのこ類)
- い=いも
これらの食材は、マグネシウムをはじめとするミネラルや食物繊維が豊富で、腸内環境の改善にもつながります。
また、玄米や雑穀米、全粒粉パンなどを主食に選ぶことで、自然とマグネシウム摂取量を増やしやすくなります。
味噌汁や納豆、豆腐などの和食メニューもおすすめです。
一方で、加工食品や清涼飲料水の摂りすぎは注意が必要です。これらにはリン酸塩などマグネシウムの吸収を妨げる成分が含まれていることがあり、せっかく摂ったマグネシウムの働きを弱めてしまうことがあります。
毎日の食卓に「自然に近い食材を多めに、精製食品を少なめに」を意識するだけで、マグネシウムのバランスが着実に整いやすくなるでしょう。
 マグネシウム不足を防ぐ食べ物ランキングTOP15|症状・原因と効果的な摂取方法を解説
マグネシウム不足を防ぐ食べ物ランキングTOP15|症状・原因と効果的な摂取方法を解説
十分な水分補給
マグネシウムの働きを保つためには、食事だけでなく水分補給も欠かせません。
体内のマグネシウムは血液や細胞内液に溶け込んで存在しており、適切な水分バランスが保たれてこそスムーズに働くことができます。
脱水状態になると、血液が濃縮されてマグネシウムの代謝が乱れやすくなり、筋肉のけいれんや疲労感が起こりやすくなります。
1日に必要な水分量は、食事に含まれる水分を除いて約1.2〜1.5リットルが目安です。
特に汗をかきやすい季節や運動時には、こまめに少量ずつ飲むことが大切です。
一気に大量の水を飲むよりも、体が吸収しやすい形で分けて摂るのがポイント。
硬水タイプの天然水には、マグネシウムが比較的多く含まれているためおすすめです。
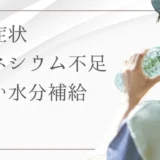 脱水症状の原因はマグネシウム不足かも|正しい水分補給とは?
脱水症状の原因はマグネシウム不足かも|正しい水分補給とは?
ストレス対策をする
ストレスは、マグネシウム不足を引き起こす大きな要因の1つです。
強いストレスを受けると、副腎からストレスホルモンが分泌されますが、このとき体は神経を落ち着かせるためにマグネシウムを大量に消費します。
そのため、ストレスが長引くほど体内のマグネシウムが減少し、さらにストレス耐性が低下するという悪循環に陥りやすくなります。
ストレスから体を守り、マグネシウムの消費量を減らすには、「心身を緩める時間」を意識的に作ることが大切です。
たとえば深呼吸やストレッチ、軽いウォーキングなどは副交感神経を優位にし、マグネシウムの消耗を抑えてくれます。
また、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かることも効果的です。
仕事や人間関係など外的なストレスに加え、「完璧主義」「我慢しすぎ」など内的なストレスにも注意が必要です。
自分を追い詰めすぎず、リラックスする時間を日常に取り入れることが、マグネシウムを守り、心と体の回復力を高める第一歩になります。
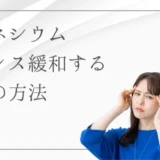 マグネシウム不足でストレスが悪化?心と体を整える現代的栄養戦略
マグネシウム不足でストレスが悪化?心と体を整える現代的栄養戦略
適度な運動
運動によって血流が促進されると、マグネシウムをはじめとするミネラルや酸素が体のすみずみまで行き渡り、細胞の代謝が活発になります。
また、筋肉を使うことでマグネシウムの需要が一時的に高まるため、体が自然にマグネシウムを取り込みやすくなるというメリットも。
ただし、ハードすぎる運動は逆効果です。
ハードな運動では汗や尿からマグネシウムが失われやすくなるほか、筋肉への負担が大きくなり、体内のバランスを崩す原因になる可能性があります。
ウォーキングやヨガ、ストレッチ、軽い筋トレなど、呼吸を意識しながら無理なく続けられる運動がおすすめです。
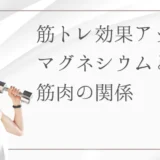 【筋トレ効果UP】マグネシウムと筋肉の関係|筋肉痛を軽減する3つの摂取法
【筋トレ効果UP】マグネシウムと筋肉の関係|筋肉痛を軽減する3つの摂取法
質の良い睡眠
マグネシウムは「自然な眠りのミネラル」とも呼ばれるほど、睡眠の質に深く関わっています。
良質な睡眠を得るためには、まず「寝る前の環境づくり」が大切です。
就寝の1〜2時間前にはスマートフォンやパソコンの使用を控え、照明を少し落として副交感神経が働きやすい状態を整えましょう。
ぬるめのお風呂に入ると体温がゆるやかに下がり、眠気が自然に訪れやすくなります。
寝る直前のカフェインやアルコールは避け、日中は適度に体を動かすこともポイントです。
マグネシウムをしっかり補い、体と心をリラックスさせる習慣を持つこと。それが、ぐっすり眠れて朝すっきり目覚める「質の良い睡眠」への近道です。
 マグネシウムが睡眠の質を左右する?不足の原因と改善方法を徹底解説!
マグネシウムが睡眠の質を左右する?不足の原因と改善方法を徹底解説!
サプリメントを活用する
食事からの摂取が難しいときや、慢性的なストレス・運動量の多い生活を送っている場合には、マグネシウムサプリメントを上手に活用することも選択肢に入れると良いでしょう。
サプリメントは手軽に補える反面、種類や摂取量を誤ると体に負担をかけることもあるため、正しい知識を持って取り入れることが大切です。
マグネシウムサプリには、「酸化マグネシウム」「クエン酸マグネシウム」「グリシン酸マグネシウム」などさまざまなタイプがありますが、吸収率が高いのは有機酸系(クエン酸、グリシン酸など)で、胃腸への刺激が比較的少ないとされています。
一方、酸化マグネシウムは便秘解消目的で使われることもありますが、体質によっては下痢を起こすこともあるため注意が必要です。
摂取の目安としては、1日あたり成人男性で約340mg、女性で約270mgが推奨量ですが、これは食事からの摂取も含めた量です。そのため、サプリメントだけで一気に補うのではなく、食事とのバランスを考えながら取り入れるよう意識しましょう。
ただし、サプリメントはあくまで補助的な栄養源です。マグネシウムをしっかり活かすには、食事・運動・睡眠といった基本の生活習慣と組み合わせることが重要です。
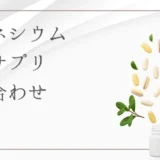 マグネシウムと鉄分のサプリの飲み合わせはNG?上手な摂取方法と注意点
マグネシウムと鉄分のサプリの飲み合わせはNG?上手な摂取方法と注意点
マグネシウム風呂を活用する
マグネシウムを入浴剤として活用する方法が「マグネシウム風呂」で、主な成分として、「エプソムソルト(硫酸マグネシウム)」や「にがり(塩化マグネシウム)」を使用します。
どちらも皮膚からマグネシウムイオンを吸収し、血流を促進して筋肉の緊張をほぐす狙いや、リラックスに役立つとされています。
特にエプソムソルトは無香料で刺激が少なく、敏感肌の人でも使いやすいのが特徴です。
使い方は簡単で、浴槽(約200L)に対してエプソムソルトを約200〜300g入れ、よくかき混ぜて15〜20分ほど浸かるだけ。
ぬるめのお湯(38〜40℃)にゆっくり入ることでリラックスしやすくなり、心身の緊張がやわらぎます。
また、マグネシウム風呂は入浴後の体の温まり方が持続しやすく、冷え感の緩和や疲労感のリフレッシュに役立つことがあります。
入浴後はしっかり水分を摂り、体を保湿すると理想的です。
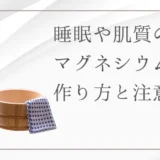 マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法
マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法
血液検査に関わるマグネシウムと他の栄養素との関係

マグネシウムは、単独で働くのではなく、他の栄養素と複雑に連携しながら体のバランスを保っています。そのため、血液検査でマグネシウム値を確認する際は、他のミネラルやビタミンとの関係性も同時に見ることが重要です。
マグネシウムとカルシウム
マグネシウムとカルシウムは、筋肉の「収縮」と「弛緩」をバランス良く調整するパートナーのような関係にあります。
カルシウムが筋肉を縮める役割を果たすのに対し、マグネシウムはそれを緩める役割を担っています。
そのため、血液検査でマグネシウムが低く、カルシウムが高い場合は、筋肉のけいれんや神経の興奮が起こりやすくなることがあります。
逆に、マグネシウムが高すぎるとカルシウムの働きが抑えられすぎ、筋力低下や低血圧のリスクが出てくることも。
血液検査では、この2つのバランスを見ることが重要です。
マグネシウムとカリウム
カリウムは細胞内に多く存在するミネラルで、マグネシウムとともに心臓や神経、筋肉の正常な働きを支えています。
マグネシウムが不足すると、カリウムが細胞内にとどまりにくくなり、血液中のカリウム濃度(血清カリウム値)が下がる「低カリウム血症」を招くことがあります。
この状態は不整脈や筋力低下の原因になるため、医師は血液検査でマグネシウムとカリウムの両方をセットで確認するのが一般的です。
マグネシウムとビタミンD
ビタミンDはカルシウムの吸収を助ける栄養素として知られていますが、活性化にはマグネシウムが欠かせません。
つまり、どれだけビタミンDを摂取しても、体内に十分なマグネシウムがなければ、その働きが十分に発揮されないのです。
血液検査でビタミンDの数値が低い場合、マグネシウム不足が背景にあるケースも考えられます。
マグネシウムと糖代謝
マグネシウムは、インスリンの分泌や働きをサポートし、血糖値を安定させる役割も持っています。そのため、糖尿病や血糖値の異常がある場合には、血液検査でマグネシウムの数値も併せてチェックされることがあります。
マグネシウムが不足すると、インスリンが効きにくくなり、血糖コントロールが乱れやすくなるとされているためです。
このように、マグネシウムの血液検査は、単独の値を見るだけでなく、「カルシウム・カリウム・ビタミンD・血糖値」との関係性を含めて評価することが欠かせません。
医師が複数の項目を同時にチェックするのは、体全体のミネラルバランスと代謝のつながりを総合的に理解するためなのです。
参照:マグネシウム摂取と糖尿病との関連について│国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト

マグネシウム検査に関するQ&A

「マグネシウム検査はどこで受けられるの?」「時間や費用はどのくらい?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、マグネシウム検査に関するよくある質問をまとめました。
マグネシウム検査はどこで受けるの?
マグネシウム検査は、一般的な内科や腎臓内科、循環器内科などの医療機関で受けることができます。
健康診断の標準項目には含まれていないことが多いため、希望する場合は医師に「マグネシウム値を測りたい」と伝えると追加検査として対応してもらえるでしょう。
また、糖尿病や心疾患、腎疾患などを治療中の方は、定期検査の一環としてマグネシウム値を測定している場合もあります。
最近では、自由診療のクリニックや人間ドックのオプション検査として受けられるところも増えています。
マグネシウム検査は誰でも受けられる?
マグネシウム検査は基本的に誰でも受けることができます。特別な条件や制限はなく、医師の判断や本人の希望によって実施されるシンプルな血液検査です。
気になる不調(こむら返り、倦怠感、不眠、動悸など)がある場合は、まずかかりつけ医に相談し、自分に必要な検査かどうかを確認するのがおすすめです。
マグネシウム検査に要する時間は?
マグネシウム検査は、一般的な血液検査の一項目として行われるため、採血自体は5分程度で終了します。
特別な装置や時間のかかる手順はなく、腕から少量の血液を採取するだけのシンプルな検査です。
検査結果が出るまでの時間は、医療機関や検査機関によって異なりますが、通常は1〜3日ほどです。即日結果を知らせてくれるクリニックもありますが、一般的には後日再診や電話での説明となるケースが多いです。
また、ほかの血液検査(電解質、腎機能、糖代謝など)と同時に行われることが多いため、結果の説明時にはマグネシウム以外のデータもあわせて確認することができます。
マグネシウム検査にかかる費用は?
マグネシウム検査の費用は、保険適用の有無によって大きく変わります。
医師が必要と判断して検査を行う場合には健康保険が適用され、自己負担はおおよそ300〜800円前後で済むのが一般的です。
一方、健康診断や人間ドックなどで任意に追加する場合や、美容・健康目的で自由診療として受ける場合は、1,000〜3,000円程度が目安となります。
クリニックによっては、カルシウムやカリウムなど他の電解質とセットになった「ミネラル検査」として提供されていることもあります。
なお、検査費用には採血料や診察料が別途加算されることがあるため、正確な金額を知りたい場合は、事前に医療機関に確認しておきましょう。
マグネシウム検査に痛みは伴う?
採血で針を刺す瞬間に「チクッ」とするだけです。
採血量もごく少量で済み、検査後は小さな絆創膏を貼るだけで終了します。
まれに内出血や軽い赤みが出る場合もありますが、数日で自然に治まるのが普通です。
サプリメントの使用は検査に影響する?
サプリメントの使用は検査結果に影響する可能性があります。
検査の直前までサプリメントを摂っていると、血中マグネシウム値が一時的に上昇し、実際より高く見えてしまうことがあるためです。
特にマグネシウム、カルシウム、鉄、亜鉛、ビタミンDなどは互いに吸収や代謝を助け合ったり、競合したりする関係にあるため、サプリの組み合わせによっても数値が変動することがあります。
そのため、検査を受ける際は医師にサプリメントの使用状況を必ず伝えることが大切です。
医師の判断によっては、検査の数日前からサプリメントの摂取を控えるよう指示される場合もあります。
どのくらいの頻度で検査を受けるべき?
マグネシウム検査の頻度は、健康状態や生活習慣によって異なりますが、基本的には年1回の健康チェックとして受けるのが目安です。
特に不調がない人でも、血圧や血糖、腎機能などとあわせて確認しておくと、自分の体のミネラルバランスを把握しやすくなります。
なお、以下にあてはまる方は、もう少し短い間隔(3〜6か月ごと)での検査がおすすめです。
- 糖尿病や腎臓病など、マグネシウムの排泄に関係する持病がある人
- 利尿剤や制酸薬、抗生物質など、マグネシウムの代謝に影響を与える薬を服用している人
- こむら返りや筋肉のけいれん、倦怠感などの症状が繰り返し起きる人
マグネシウムは体にとって欠かせないミネラルですが、血中濃度はごくわずかしかないため、数値の変化は自覚しにくいものです。
年に一度のチェックを習慣にして、早めに不調のサインを見逃さないようにしましょう。
まとめ|マグネシウムが不足しない健康な状態を目指そう

マグネシウムは、私たちの体の生理機能を多面的に支える基礎ミネラルです。ですが、現代の食生活やストレス社会では、不足しがちな栄養素でもあります。
血液検査を通じてマグネシウム値を確認することは、自分の体のバランスを知る大切なステップです。数値が少しでも基準から外れている場合、それは「体からの小さなサイン」かもしれません。
生活習慣の見直しや、食事・水分・睡眠の整え方を意識して、体を正常な状態に導いてあげることが大切です。
また、カルシウムやカリウム、ビタミンDなど、他の栄養素とのバランスも健康維持には欠かせません。
単に不足を補うのではなく、体全体の調和を意識することが、長く健やかに過ごすためのポイントです。
マグネシウム検査に抵抗がある方は、まずは簡単な「マグネシウム不足セルフチェック」で、ご自分の状態をチェックしてみてください。