マグネシウムは、筋肉や神経の働きをサポートし、血圧や体温の調整にも関わる重要なミネラルです。
しかし、現代の食生活では不足しがちであり、厚生労働省の調査でも約70%の人が推奨摂取量を満たせていないことが指摘されています。
本記事では、マグネシウムを豊富に含む食品TOP24をランキング形式で紹介し、効率的な摂取方法や献立例も解説します。
「普段の食事でマグネシウムをしっかり摂れているか気になる」
「不足しがちな栄養素を効率よく補いたい」
という方は、ぜひ最後までチェックしてみてください!
マグネシウムが豊富な食品の効果

マグネシウム食品ランキング上位の食材は、健康維持に役立つ栄養を多く含みます。
そうした食品には、以下のようなさまざまな効果が期待されます。
- 筋肉の収縮(筋肉を緩める)
- 神経伝達物質をスムーズに運ばせる
- 体温や血圧の調整
- 骨への影響や関節炎の改善
- 不整脈や狭心症の改善サポートや予防
- 高血圧や筋肉のけいれんの改善
- 足などが「つる」「こむら返り」を抑える
- リラックス作用
- 便を柔らかくする
近年の研究では、マグネシウムが体に与える影響について、以下のようなことがわかっています。
Currently, enzymatic databases list over 600 enzymes for which Mg2+ serves as cofactor, and an additional 200 in which Mg2+ may act as activator. (訳:現在、酵素データベースには、Mg2+が補因子として機能する酵素が600以上リストされており、さらにMg2+が活性化剤として機能する可能性のある酵素が200以上リストされています。
Magnesium in Man: Implications for Health and Disease | Physiological Reviews?
つまり、マグネシウムが関与する酵素の働きは約800種類にも及び、私たちの体内で重要な役割を果たしているのです。
マグネシウムが豊富な食材の効果については、下記の記事でさらに詳しく紹介しているので、こちらも併せてチェックしてみてください。
 マグネシウムの効果とは?ミネラル豊富な食品と吸収率を高める摂取方法・注意点を解説
マグネシウムの効果とは?ミネラル豊富な食品と吸収率を高める摂取方法・注意点を解説
マグネシウムが不足すると、以下のような症状が現れることがあります。
- 足がつりやすい
- ストレスを感じる
- 瞼がぴくぴくと軽くけいれんする
- 睡眠の質がよくない
こうした症状が気になる場合は、まずは日々の食生活を見直し、マグネシウムを意識的に摂取することが大切です。
マグネシウムが不足する原因については、以下の記事でやさしく解説しているので、参考にしてください。
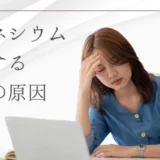 マグネシウム不足の5つの原因と症状|正しい摂取方法も解説
マグネシウム不足の5つの原因と症状|正しい摂取方法も解説
マグネシウムが豊富な食材・食品ランキングTOP24

マグネシウムを多く含む食材・食品TOP24をランキング形式で紹介します。
各食材・食品の数値は100gあたりのマグネシウム含有量を示しています。
なお、「素干し」や「乾燥」と表記された食材は調理時に水分を含むため、実際に摂取できるマグネシウム量が減少する点にご注意ください。
| 食品名 | マグネシウム含有量 |
|---|---|
| あおさ 素干し | 3200mg |
| あおのり 素干し | 1400mg |
| ひじき 乾燥 | 640mg |
| 昆布 素干し | 490mg |
| えんどう豆 乾燥 | 360mg |
| ごま(生) | 351mg |
| いわのり 素干し | 340mg |
| カシューナッツ(生、無塩) | 292mg |
| あわ | 270mg |
| アーモンド(生、無塩) | 268mg |
| きなこ | 260mg |
| 黄色大豆 乾燥 | 220mg |
| 玄米(生) | 143mg |
| 全粒粉 | 140mg |
| 木綿豆腐 | 130mg |
| あずき 乾燥 | 120mg |
| 玄米 | 110mg |
| ほうれん草(生、葉のみ) | 79mg |
| ハバネロペッパー(生) | 76mg |
| えだまめ ゆで | 72mg |
| マッシュルーム(生) | 42mg |
| サケ(生) | 27mg |
| バナナ | 27mg |
| ヨーグルト | 11mg |
参考:「日本食品標準成分表」文部科学省
ランキング上位の海藻・豆類・穀類・ナッツを少量ずつでもいいので、分散して取り入れるようにすると、日々のマグネシウム摂取量を底上げしやすくなるでしょう。

【参考例】マグネシウム豊富な食品ランキングを参考に食事に取り入れてみた

マグネシウムを多く含む食品をランキング形式で紹介しましたが、実際の食事に取り入れるとどのような違いが生まれるのでしょうか?
今回は、「一般的な現代の食事」と、「マグネシウムを意識した食事」を比較し、その栄養バランスの違いを検証します。
例として、インスタグラムで投稿されていた30代半ばのOL女性(Aさん)の1日の食事を取り上げます。
以下はAさんの基本情報です。
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 52kg |
| 1日の推奨摂取カロリー | 2148kcal |
| 推奨マグネシウム摂取量 | 310〜320mg |
ここから、実際の食事を見ていきましょう。
【一般的な現代の食事例】
Aさんが実際に食べていた、ある1日の食事内容です。
| 朝 | ロールパン×2、スクランブルエッグ、ヨーグルト、カフェオレ |
| 昼 | カルボナーラスパゲッティ、サラダ |
| 夜 | 白米、唐揚げ、ポテトサラダ、味噌汁 |
しっかり朝食も摂り、昼食にはサラダも摂り入れ、夜も自炊しています。
バランスよく食べているように見えますが、栄養データを確認すると以下のような結果になりました。
| 項目 | 摂取量 | 推奨量 |
|---|---|---|
| カロリー | 2315kcal | 2148kcal |
| タンパク質 | 101g | 81g |
| 脂質 | 129g | 60g |
| 炭水化物 | 208g | 322g |
| 食物繊維 | 15g | 18g |
| マグネシウム | 234mg | 320mg |
マグネシウムが不足し、カロリーと脂質が大幅にオーバーしています。
また、さらに詳しくデータを見ると、
- 脂質の中でもコレステロール値が特に高く、また塩分過多
- カリウム、カルシウム、鉄などのミネラルの摂取不足
- ビタミンD、ビタミンB1、ビタミンB6、ビタミンCなどのビタミンの摂取不足
という結果となりました。
今回の例だけに限らず、現代の食事は一見バランスが取れているように見えますが、マグネシウム不足や、その他ミネラルやビタミンなどの補酵素も不足しがちであり、コレステロールや塩分の摂取量が多くなりやすい傾向があります。

【マグネシウム豊富な食品・食材を摂り入れた献立例】
では、マグネシウムをしっかり摂取できる食事を考えてみましょう。
1日のマグネシウム推奨摂取量(320mg)を満たすよう、先ほどのランキングの食材を使って献立を作成しました。
| 朝 | 全粒粉パン、目玉焼き、バナナ、コーヒー |
| 昼 | きなこもち、ヨーグルト、フルーツサラダ |
| 夜 | 玄米、焼き魚(さけ)、ほうれん草のお浸し、海藻の味噌汁 |
和食を中心に栄養バランスを意識した献立ですが、実際の栄養データを確認してみましょう。
| 項目 | 摂取量 | 推奨量 |
|---|---|---|
| カロリー | 1270kcal | 2000kcal |
| タンパク質 | 67g | 80g |
| 脂質 | 29g | 59g |
| 炭水化物 | 200g | 322g |
| 食物繊維 | 13g | 18g |
| マグネシウム | 320mg | 320mg |
マグネシウムは摂取推奨量の320mgをクリアしましたが、以下の問題が出てきました。
- 2000kcalを目安としなければならない摂取カロリーを大幅に下回っている
- 炭水化物、食物繊維が摂取不足
- 鉄、亜鉛などのミネラルが摂取不足
- ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンCなどの摂取不足
現代の一般的な食事はカロリー・脂質が過剰になりやすい傾向がありますが、マグネシウムを意識した食事ではカロリーや一部の栄養素が不足してしまうことが分かります。
マグネシウムは健康維持に欠かせない栄養素ですが、単一の栄養素にこだわりすぎると、他の栄養素が不足してしまう可能性があります。
特に、玄米や海藻は満腹感を得やすい食品のため、必要なカロリーが摂取できず、栄養不足になるリスクもあります。
ここまで摂取カロリーが低くその他の栄養素も足りていないと、栄養失調の恐れが出たり、肌や髪などにダメージが出て、美容面でも健康面でもよくありません。
そのため、食事全体のバランスを考えつつ、必要に応じてサプリメントなどで補うことも選択肢の一つです。
欧米では医療現場や一般家庭でマグネシウムの重要性が知られており、サプリ製品などが日常的に使われています。
それに対して、日本ではまだまだ認知度が低いというのが現状です。
以下のオーガニックサイエンスの公式YouTubeチャンネルでは、海外と日本のマグネシウム認知度やサプリなどの普及度の差について「日本オーソモレキュラー医学会」代表理事の柳澤厚生(あつお)先生が、詳しく解説しています。
こちらも併せてご覧ください。
マグネシウムが不足しがちな日本人

日本人の多くは、マグネシウムが不足しているといわれています。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書によると、
・男性の平均摂取量:236mg/日(推奨量370mg) → 約37%不足
・女性の平均摂取量:205mg/日(推奨量290mg) → 約30%不足
つまり、多くの人が推奨摂取量に達しておらず、日常的にマグネシウム不足の状態です。
参考:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書|厚生労働省
また、マグネシウム研究の第一人者で「Dr.マグネシウム」との呼ばれる医師の横田邦信先生は、日本のマグネシウム検査基準について、次のように指摘しています。

「マグネシウムの採血検査において、現在の基準値の下限が甘すぎるため、低マグネシウム血症の診断が過小評価される危険性があります。長い目で健康を考えると、この基準は好ましくないと言えます。現在の日本の多くの基準値が1.8~2.6㎎/㎗ですが、私どもは2022年にグローバルな標準化の推奨を報告しました。低マグネシウム血症の推奨値:2.06~2.33㎎/㎗としています」
つまり、現在の基準値では「正常範囲でも、実はマグネシウムが不足している可能性がある」ということです。
基準値自体も見直しが必要だと言われているマグネシウム。
食事の見直しはもちろん、別の方法でマグネシウムを補う必要がありそうです。

マグネシウムが豊富な食品とサプリメントを併用しよう

マグネシウムは私たちの体内の800以上の酵素反応に関わり、健康維持に欠かせないミネラルの一つです。
しかし、食事だけで推奨量を満たすのは難しいこともあります。
そこで、食事とサプリメントを組み合わせて効率的に摂取することが重要です。
次章ではランキングで紹介した食材を活用しつつ、食事だけでは補いきれない部分をサプリメントでサポートする方法をご紹介します。
マグネシウム豊富な食品とサプリの併用方法①摂取方法

マグネシウムは毎日摂取することが大切なミネラルです。
しかし、人によっては「気持ちが悪くなる」「飲みにくい」「匂いがきつい」など、継続するのが難しいと感じる方もいます。
そのため、まずはどんな方法でマグネシウムを摂取できるのか確認し、自分に合ったマグネシウムの摂取方法を選択できるようにしましょう。
マグネシウムの摂取方法には、主に経口摂取と経皮摂取の2種類があります。
経口摂取とはサプリメントと同じ方法で、口から摂取する方法です。
もう一つの経皮摂取(経皮吸収)とは、マグネシウムを皮膚から吸収することを指します。
特に、足がつりやすい(こむら返りしやすい)、歯ぎしりや睡眠の質が気になる、イライラしてこめかみがきしむ、などのマグネシウム不足の症状でお悩みの場合には、経皮からマグネシウムを吸収するのもおすすめです。
経皮吸収については以下の記事で詳しく取り上げているので、こちらも併せてご覧ください。
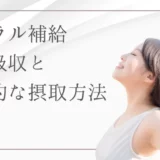 経皮吸収とは?肌から成分が吸収される仕組みを分かりやすく解説
経皮吸収とは?肌から成分が吸収される仕組みを分かりやすく解説
マグネシウム豊富な食品とサプリの併用方法②肝臓を労わる

マグネシウムのサプリメントを含む栄養補助食品は、多くの場合、一度肝臓で代謝されてから血液に成分が送られます。
これは、一般的な化学薬品と同じ経路をたどるため、肝臓に負担をかける可能性があるのです。
よくサプリメントを飲んで気分が悪くなるという人は、胃などの消化器が疲れている他、肝臓が弱っている可能性も考えられます。
そのため、肝臓で代謝されるサプリメントの裏表示には「肝臓に疾患がある方は使用を控えてください」などと注意喚起をしているのです。
こうしたリスクを抑え、肝臓を経由せずに体内へ直接吸収される製法のひとつがリポソームを用いた製法です。
もともとは医薬品などが消化されないよう確実に体に届くように開発された製法ですが、最近ではビタミン剤などのサプリメントや化粧品にもこの技術がとり入れられています。
食事で充分な栄養を補えない時には、できるだけ体に優しく負担が少ないリポソーム製法のサプリメントを摂り入れるようにしましょう。
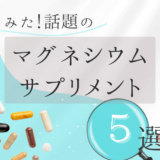 マグネシウムサプリメントのおすすめ5選|吸収率で選ぶ失敗しないコツ
マグネシウムサプリメントのおすすめ5選|吸収率で選ぶ失敗しないコツ
まとめ|マグネシウムが豊富な食品ランキングを活用して食生活を改善しよう
マグネシウムは、筋肉や神経の働きをサポートし、体のバランスを整える重要なミネラルですが、現代の食生活では不足しがちです。
今回のマグネシウムを豊富に含む食品ランキングを活用して、自分に合った方法で無理なく摂取し続けることが大切です。
その際は、一つの方法だけに固執するのではなく、「食事・サプリメント・経皮吸収」など柔軟に組み合わせて摂取するとよいでしょう。
まずは試しに毎日の食事を少しずつ見直し、マグネシウムを含む食品を意識的に摂ることから始めてみましょう!




