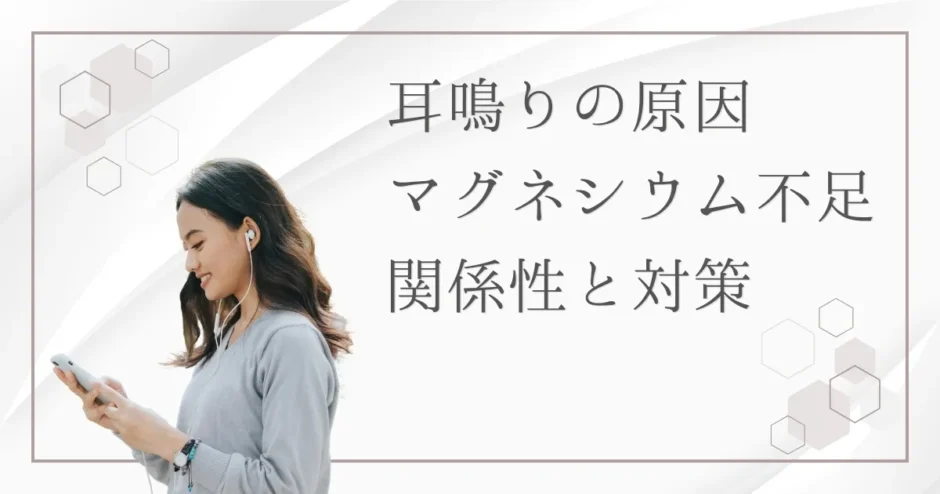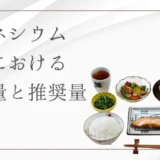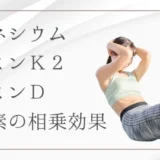静かな場所でふと「キーン」「ジー」といった音が耳の奥で鳴り続ける…そんな経験をしたことはありませんか?
それは、耳鳴りと呼ばれる症状かもしれません。
日常の中でのふとした瞬間に耳鳴りに気付く──という程度であれば問題ありませんが、耳鳴りが慢性的になってくると集中力や睡眠の妨げとなり、日常生活に支障をきたす場合もあります。
命に関わる症状ではないものの、気になり始めてしまうと厄介ですよね。
耳鳴りの原因は、ストレスや疲労、肩こり、加齢といった身近なものから、外傷や内耳の病気、さらには後遺症によるものなどさまざまな要素が考えられます。
このように複合的な要因が絡み合う耳鳴りですが、実は近年、マグネシウム不足が隠れた原因の一つとして注目されているのをご存知でしょうか?
マグネシウムは、ストレスや血流、神経の働きに関わる重要なミネラル。現代人に不足しやすい栄養素でもあるため、耳鳴りに悩む方は一度、食生活やサプリメントでの補給を見直してみても良いかもしれません。
今回は、耳鳴りの原因やマグネシウムとの関係性、効率的な摂取方法などをわかりやすく解説します。つらい耳鳴りから解放されたいと感じている方は、ぜひ参考にしてください。
耳鳴りの原因とは?

はじめに、耳鳴りの原因について解説します。
先述したように耳鳴りの原因はさまざまで、主に以下のようなものが考えられます。
- ストレス
- 疲労
- 加齢による聴覚機能の衰え
- 肩こりや首こりによる血流障害
- 外傷(爆音や事故など)
- 内耳や脳の病気(突発性難聴、メニエール病など)
- 薬剤の副作用や病気の後遺症
これらの中でも、ストレス・疲労・加齢・肩こりなどは、生活習慣の改善や栄養補給によってある程度予防・改善が可能です。
つまり、日常のちょっとした工夫で耳鳴りの負担を軽減できる可能性があるのです。
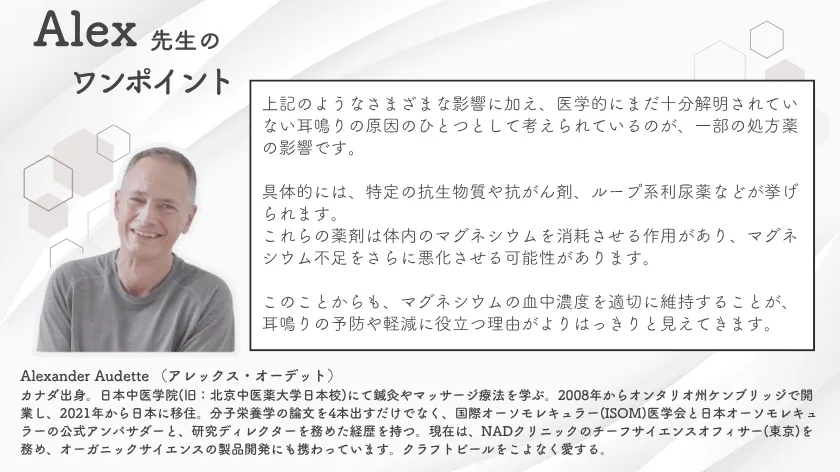
上記のようなさまざまな影響に加え、医学的にまだ十分解明されていない耳鳴りの原因のひとつとして考えられているのが、一部の処方薬の影響です。
具体的には、特定の抗生物質や抗がん剤、ループ系利尿薬などが挙げられます。これらの薬剤は体内のマグネシウムを消耗させる作用があり、マグネシウム不足をさらに悪化させる可能性があります。
このことからも、マグネシウムの血中濃度を適切に維持することが、耳鳴りの予防や軽減に役立つ理由がよりはっきりと見えてきます。
耳鳴りへの対策
耳鳴りの原因に対処する方法として、はじめに意識したいのがストレスマネジメントや血流改善、神経の安定化です。
ここで、注目されているのがマグネシウムの役割です。
マグネシウムは、内耳の血流を改善したり、神経の過敏さを抑えたりする働きがあるため、耳鳴りの予防や軽減に役立つと言われています。
次項からは、マグネシウムと耳鳴りの深い関係について、さらに詳しくご紹介します。
マグネシウムと耳鳴りの関係性

耳鳴りとマグネシウムには、どのような因果関係があるのでしょうか。
マグネシウムと耳鳴りの関係性について、体の仕組みから詳しく解説していきます。
内耳の血流改善
耳鳴りは、内耳やその周辺の血流が悪くなることでも起こりやすくなるとされています。
一方、マグネシウムには血管を拡張し、血流をスムーズにする作用があるため、内耳への血液供給を改善する働きが期待できます。
つまり、マグネシウムを摂取して血流が改善されることで、酸素や栄養素が耳の神経にしっかり届き、耳鳴りの症状が和らぐ可能性がある──ということです。
もちろん、マグネシウムを摂取することで予防や改善に期待できるのは耳鳴りだけではありません。
マグネシウムは、体内における実に800以上の酵素活動に関与しているといわれており、私たちの心身の健康をサポートしています。
健康的なライフスタイルを目指すために、マグネシウムを意識的に摂取する習慣をつけたいですね。
神経過敏を鎮める
マグネシウムは、神経の興奮を抑えるミネラルとしても知られています。
マグネシウムが不足すると神経が過敏になり、耳鳴りだけでなく、手足のしびれやこむら返りなど、さまざまな神経症状を引き起こす原因になることも。
マグネシウムをしっかり補給することで、過敏になった神経の働きを落ち着かせ、耳鳴りの不快感を軽減できる可能性があります。
ストレスへの影響
現代人の耳鳴りの大きな原因の一つとして考えられるのが「ストレス」です。
ストレスがかかると、「抗ストレスミネラル」と呼ばれる体内のマグネシウムが大量に消費されてしまいます。
そのため、慢性的なストレス状態ではマグネシウム不足になりやすく、さらに神経の興奮や血流障害が悪化して耳鳴りが強くなる…という悪循環に陥ってしまうのです。
ストレス対策としても、マグネシウム補給は有効といえるでしょう。
マグネシウム不足の主な症状

マグネシウムが不足すると、耳鳴り以外にもさまざまな不調が現れる場合があります。
ここでは、マグネシウムが不足した場合の主な症状について解説します。
マグネシウム不足のサイン
マグネシウムが不足すると、耳鳴り以外にも以下のような体調不良が現れることがあります。
- こむら返り
- 筋肉のけいれん
- 慢性的な疲労感
- 頭痛
- イライラや不安感
- 集中力の低下
- 便秘
こうした症状が気になる方は、マグネシウム不足を疑ってみても良いかもしれません。
低マグネシウム血症の症状
さらに深刻なマグネシウム不足である「低マグネシウム血症」になると、次のような症状が現れます。
- 食欲不振
- 吐き気、嘔吐
- 手足のしびれ
- 心拍異常
- けいれん
- 性格の変化(不安、抑うつなど)
低マグネシウム血症は放置すると危険な状態になるため、気になる症状が続く場合は、医師の診断を受けることが大切です。
マグネシウム不足を招く主な原因
マグネシウム不足の背景には、以下のような要因があります。
- ストレス過多
- 偏った食生活
- アルコールの過剰摂取
- 糖尿病、胃腸疾患、腎臓疾患など
- 利尿剤や一部の薬剤の副作用
「ストレス社会」と呼ばれるようになって久しい日本社会。
日ごろのストレスを解消するため夜な夜なお酒を飲みに出掛けたり、多忙で自炊が難しく、つい外食やコンビニ弁当に頼ってしまったりしている人も多いでしょう。
現代人の生活習慣そのものが、マグネシウム不足を招きやすい構造になっていることを思えば、日ごろから意識的にマグネシウムを摂取することの大切さがうかがえます。
マグネシウムを効果的に摂取するには

マグネシウムが健康や耳鳴り対策に重要だとわかっても、実際にどのように摂取すればよいのか迷ってしまいますよね。
食事からしっかりと摂るのが基本ですが、忙しい毎日の中ではなかなか難しいこともあります。
ここでは、日常生活の中で無理なくマグネシウムを摂取するための方法や注意点について、わかりやすく解説します。
食事の栄養バランスに配慮する
マグネシウムの摂取は、食事を通して自然な形で行えるのが理想的です。
マグネシウムを多く含む食品としては、次のようなものがあげられます。
- 玄米
- 大豆製品(納豆、豆腐、きなこなど)
- 海藻類(わかめ、ひじきなど)
- ナッツ類(アーモンド、カシューナッツ)
- 緑黄色野菜(ほうれん草、小松菜)
特に日本の伝統的な和食は、マグネシウムを豊富に含む食材が多いため、積極的に取り入れたいところです。
 【24選】マグネシウムを豊富に含む食品ランキング|効率的な摂取方法&簡単献立例
【24選】マグネシウムを豊富に含む食品ランキング|効率的な摂取方法&簡単献立例
サプリメントを活用する
忙しくて食事だけでは補いきれない場合は、サプリメントを活用するのも効果的です。
ただし、過剰摂取には注意しましょう。
1日のマグネシウム摂取量の目安は成人で300~400mg程度とされています。
サプリメントの過剰摂取により、下痢や腹痛を引き起こすことがあるため、用法・用量を守ることが大切です。
生活習慣を工夫する
ストレスを減らすこともマグネシウム不足の予防につながります。
十分な睡眠や適度な運動、趣味の時間を取るなど、無理なく実践できるリラックス習慣を心掛けましょう。
マグネシウムを摂取する上での注意点
胃腸が弱い方は、マグネシウムサプリメントを少量から利用するのが安心です。
また、腎臓病や糖尿病の方は、マグネシウムの排出や代謝がうまくいかない場合があるため、必ず医師と相談しながら摂取することをおすすめします。
耳鳴り軽減のために│その他のアプローチ

マグネシウムだけに頼らず、日常生活の中でできる耳鳴り対策も取り入れましょう。
心身のコンディションを整えて耳鳴りの予防に努めるなら、以下のような取り組みがおすすめです。
- 質の良い睡眠を確保する
- 軽い運動で血流を促す
- ストレス軽減のために瞑想や深呼吸を取り入れる
- カフェイン・アルコールの摂取を控える
- 定期的に耳鼻科を受診して内耳の状態をチェックする
こうした習慣を積み重ねることで、耳鳴りを感じにくい体質づくりが目指せます。
まとめ|マグネシウム活用で耳鳴りに「さよなら」を

耳鳴りは、誰にでも起こりうる身近な不調ですが、原因や対策を知っていれば、怖いものではありません。
特に現代人に不足しがちなマグネシウムは、耳鳴り対策の大切なポイントです。
食事やサプリメント、生活習慣の見直しを通して、マグネシウムをしっかり補っていきましょう。
耳鳴りのない静かな日常を取り戻すために、まずはできることから始めてみませんか?