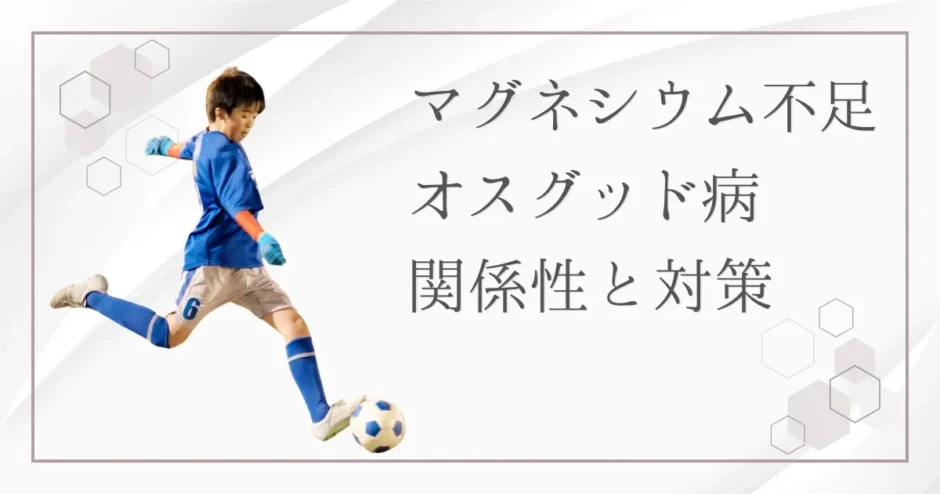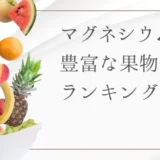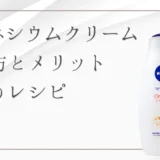成長期の子どもに多い「オスグッド病(オスグッド・シュラッター病)」は、膝のお皿の下あたりに痛みや腫れが生じることがあるスポーツ障害の一つです。
成長期の子どもは、骨の成長に伴って“成長痛”による膝の痛みを訴えるケースも多く、オスグッド病を見逃してしまうことがあります。
たとえばお子さんが「膝が痛い」と言ったら、「成長痛だろう」と自己判断せず、整形外科などの専門医に相談することが大切です。
オスグッド病は、特にサッカーやバスケットボールのようにジャンプや走る動作が多いスポーツをしている子どもに多く見られます。
膝の痛みを訴えるケースが一般的で、練習を続けるのがつらくなる場合も。
成長期の骨や筋肉は大きく発達する一方で負担もかかりやすいため、このような障害が起こりやすいといわれています。
一方で、成長期に欠かせない栄養素の一つとして「マグネシウム」が注目されています。
マグネシウムは骨や筋肉の形成に関わるミネラルであり、日々の食生活の中で不足しやすいといわれています。
日常的にバランスの良い食事を意識し、必要な栄養素をしっかり取り入れることは、子どもの健やかな成長を支える上で大切です。
今回は、オスグッド病の基本や原因を整理しながら、成長期に大切な栄養素であるマグネシウムを含めた生活習慣についてご紹介します。
オスグッド病とは?

オスグッド病がどんな病気なのか、育ち盛りのお子さんをお持ちの親御さんには、決して他人事ではないトピックですよね。
スポーツを楽しむ子であればなおさらです。
まずはオスグッド病がどんな病気で、どのような条件で発症しやすいのか、その原因とリスクについて解説します。
オスグッド病はどんな症状?
オスグッド病は、膝のお皿(膝蓋骨)のすぐ下にある「脛骨粗面(けいこつそめん)」と呼ばれる部分に炎症が起こり、痛みや腫れを伴うのが特徴です。
脛骨粗面は、下の写真のちょうど指を差している部分です。

オスグッド病は特に成長期の子どもに多く見られ、走る・跳ぶ・しゃがむといった動作の際に強い痛みが出ることがあります。
初期段階では運動後に「膝の下が少し痛む」程度ですが、進行すると練習中や日常生活の歩行時にも痛みを感じることがあります。
外見上は膝の下が盛り上がって見えることがあり、触れると硬く出っ張っていたり、押すと痛みが強まる場合もあります。
症状は片側に出ることもあれば、両膝に出ることもあります。
特に運動量が多い子どもや、成長スピードが速い子どもでは両膝に症状が出やすい傾向があります。
日常生活に大きな支障をきたすことは少ないものの、しゃがみ込みや階段の上り下りがつらくなるケースも。
また、痛みが一時的に治まることもありますが、成長期が終わるまで繰り返す場合があるのも特徴です。
そのため、痛みが出た時点で無理をして運動を続けると悪化しやすく、症状が長引くこともあります。
子ども自身は「少し痛いけど頑張れる」と思ってしまいがちですが、症状が続く場合は休養を取り、必要に応じて整形外科など専門医に相談することが重要です。
発症しやすい年齢・性別・スポーツ
| 発症しやすい年齢 | 10〜15歳の成長期に多い(特に小学校高学年〜中学生) |
| 発症の性別割合 | 男子に多い(女子の約2〜3倍とされる) |
| 発症例が多いスポーツ種目 | サッカー、バスケットボール、バレーボール、陸上競技などジャンプやダッシュの多い競技 |
| 発症割合の目安 | スポーツを活発に行う成長期の子どもの10〜20%程度が経験するとされる |
| 具体的なリスク要因 | 練習量が多い、休養不足、筋肉の柔軟性不足、急激な身長の伸び、フォームの偏り |
オスグッド病は、主に10〜15歳ごろの成長期に多く見られるとされています。
特に小学校高学年から中学生にかけて、身長が急激に伸びる時期は注意が必要です。
この時期は骨の成長スピードに比べて筋肉や腱の伸びが追いつかず、筋肉が硬くなりやすい傾向があります。
そのため、大腿四頭筋が脛骨粗面を強く引っ張ることで炎症につながるケースがあると考えられています。
性別では、男の子に比較的多いとされています。
理由の一つとして考えられるのは、成長スピードが急であることや、サッカー・バスケットボール・野球など膝に負担のかかるスポーツに取り組む割合が高い点です。
ただし近年は、女の子でもクラブ活動や部活動でハードな練習を行う機会が増えており、オスグッド病を発症するケースも少なくありません。
特にバレーボールや陸上競技、ダンスなど、ジャンプや踏み込み動作を繰り返すスポーツでは注意が必要です。
代表的なスポーツとしては、サッカー・バスケットボール・バレーボールがあげられます。
これらはジャンプやダッシュ、急なストップ動作が多く、膝に負担がかかりやすいのが共通点です。
また、陸上競技の短距離やハードル、野球やテニスのように踏み込み動作を繰り返す競技でも見られることがあります。
さらに、練習量が多く休養が十分に取れていない場合は、症状が出やすいといわれています。
背景には「成長期」という体の特性が大きく関わっており、筋力や柔軟性が未発達な状態で急激に運動量が増えることで膝に負担がかかりやすくなると考えられています。
発症しやすい年齢・性別・スポーツの特徴を理解し、該当する子どもが痛みを訴えた場合には、無理をせず休養を取り、必要に応じて整形外科などの専門医に相談することが大切です。
オスグッド病の原因とリスク
オスグッド病の大きな要因の一つは、成長期に見られる「骨と筋肉の成長スピードの差」といわれています。
急激に骨が伸びる一方で、筋肉や腱の成長が追いつかず硬くなりやすいため、大腿四頭筋が膝下の脛骨粗面を強く引っ張り、炎症や痛みにつながることがあると考えられています。
リスク要因としては、まず「練習量の多さや休養不足」があげられます。
十分に回復する前に運動を続けると、膝への負担が増して症状が長引く可能性も。
また「柔軟性の不足」も影響するとされています。
ストレッチを行わないと筋肉のこわばりが強まり、膝にかかる負荷が大きくなる場合があるのです。
さらに「急激な身長の伸び」も典型的なリスク要因と言えるでしょう。
成長期特有のアンバランスさによって筋肉や腱が硬直しやすくなるため、この時期に運動量が多いと症状が出やすいといわれています。
加えて、「体の使い方の偏り」も要因の一つとされています。
たとえば、片脚に体重をかける癖やジャンプ時のフォームの乱れなどは、膝に余分な負担をかける要素となる場合があります。
マグネシウムの働きとは?

オスグッド病は、膝にかかる負担が大きな要因とされていますが、成長期の子どもにとっては日々の生活習慣や食事も体づくりに影響を与えます。
中でもマグネシウムは、骨や筋肉の形成に関わるミネラルの一つとして知られています。
日本人は食生活の変化によりマグネシウムを摂取する量が不足しがちだといわれており、成長期の子どもにおいてもバランスの良い食事を意識することが大切です。
ここからは、マグネシウムが体の中でどのような役割を担っているのかを見ていきましょう。
骨・筋肉の成長をサポート
マグネシウムは、成長期の子どもにとって重要な栄養素の一つです。
骨の健康といえば「カルシウム」がよく知られていますが、実は骨づくりにはカルシウムだけでなく複数の栄養素が関わっています。
マグネシウムはその中でカルシウムの代謝に関わり、栄養バランスを整える上で大切な役割を持つとされています。
また、マグネシウムは筋肉の働きにも関わることが知られています。
筋肉はカルシウムによって収縮し、マグネシウムによって弛緩するサイクルを繰り返しているため、どちらもバランスよく摂取することが推奨されています。
成長期は骨や筋肉が急速に発達する時期であり、栄養バランスの良い食事を心がけることが健やかな成長につながります。
特にスポーツをしている子どもは、日々の食事から十分なエネルギーやミネラルを摂ることが大切です。
筋肉のこわばり・けいれん予防
マグネシウムは「天然のリラックスミネラル」とも呼ばれるほど、筋肉のスムーズな働きに欠かせない存在です。
体内のミネラルバランスが崩れると、筋肉が硬直したままになったり、突然けいれんを起こしたりすることも(ただし、これらの要因は運動習慣や水分・ミネラルのバランスなどさまざまで、一つに特定できるものではありません)。
マグネシウムは現代の食生活では不足しがちといわれているため、バランスのとれた食事の中で意識して摂取することが大切です。
炎症の抑制やストレス対策にも
マグネシウムは骨や筋肉をサポートするだけでなく、「炎症を抑える働き」や「心身のストレスを和らげる作用」などを含め、体内でさまざまな働きを担っています。
成長期の子どもは練習や試合で体に負担をかけやすく、その結果として膝まわりの炎症が起こりやすい状態にあります。
マグネシウムには炎症性サイトカインと呼ばれる物質の過剰な働きを抑える作用があるとされており、炎症を長引かせず、回復をサポートする役割を果たしてくれるのです。
また、マグネシウムの“精神面でのサポート力”も見逃せません。
「天然のリラックスミネラル」と呼ばれる通り、ストレスにさらされる現代人に欠かせない栄養素なのです。
成長期の子どもは、学校生活や部活動で多忙な毎日を過ごし、心身のストレスを抱えやすい傾向があります。
マグネシウムをはじめとするミネラルやビタミンを日常的に意識することは、毎日の健康づくりにもつながります。

マグネシウム不足とオスグッドの関係

次に、成長期の子どもにとって大切な栄養素の一つであるマグネシウムについて、体内でどのような役割を担っているのか、そして不足するとどのような影響が考えられているのかを具体的に見ていきましょう。
筋肉の柔軟性が低下する可能性
マグネシウムは、筋肉の伸び縮みにも関わるミネラルの一つとされています。
不足すると筋肉がスムーズに働きにくくなる場合があるため、日々の食事から意識して摂取することが大切です。
特に成長期の子どもは運動量が多く、サッカーやバスケットボールのようにダッシュやジャンプを繰り返すスポーツでは筋肉に大きな負担がかかります。
そのため、栄養バランスのとれた食生活を心掛けることが、健やかな成長を支えるうえで重要といえるでしょう。
疲労の蓄積や回復の遅れが生じる可能性
運動後の体のケアでは、栄養や休養をしっかり取ることが大切です。
中でもマグネシウムは、筋肉やエネルギー代謝に関わるミネラルの一つとして知られています。
激しい運動をすると「疲れが抜けにくい」「翌日に筋肉が重い」と感じることがありますが、その背景には運動量や休養の取り方、食事のバランスなどさまざまな要因が関わっており、ミネラル不足が一因となる可能性も。
成長期の子どもにとって、日常的にバランスの良い食事や十分な休養を心掛けることが、健やかな体づくりにつながります。
マグネシウムを補うためにできる3つのこと

マグネシウムを補う基本は、毎日の食事から摂取することです。
マグネシウムはさまざまな食品に含まれていますが、特に多いのは海藻類(わかめ、ひじき、昆布)、大豆製品(豆腐、納豆、きな粉)、ナッツ類(かぼちゃの種、アーモンド、カシューナッツ)、そして玄米や雑穀などの未精製の穀物です。
これらを食事に取り入れることで、自然にマグネシウムの摂取量を増やすことができます。
現代の食生活では、白米や精製された小麦粉を中心に食べることが多いため、マグネシウムが不足しやすい傾向にあるといわれています。
たとえば、白米と玄米を比較すると、玄米にはおよそ3倍以上のマグネシウムが含まれています。
毎日の主食を少し雑穀入りにするだけでも、マグネシウムを摂取しやすくなります。
また、成長期の子どもはカルシウムを多く摂ることが推奨されますが、カルシウムだけを意識して牛乳やチーズを増やすと、マグネシウムとのバランスが偏ることもあります。
骨の健康を考える上では、カルシウムとマグネシウムをおおよそ「2:1」の割合で摂取するのが望ましいとされることがあるため、乳製品を多く食べるときには豆腐や海藻、ナッツなどを組み合わせるのがおすすめです。
マグネシウムを豊富に含む食品や献立例については「マグネシウムを効率よく摂る方法!豊富な食品ランキング&簡単献立例」で詳しく解説していますので、参考にしてください。
 マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説
マグネシウムの効果とは?体に効く理由と効率的な3つの摂取方法を完全解説
マグネシウムサプリやバスソルトを活用する
理想は食事から十分なマグネシウムを摂ることですが、忙しい日常の中では意識しないと不足しがちになることもありますよね。
特に成長期の子どもは運動量が多いため、毎日の食事の中で栄養バランスを意識することが大切です。
食事だけで十分に摂れないと感じる場合には、サプリメントやマグネシウム入りの入浴剤を活用する方もいます。
マグネシウムサプリは、錠剤・粉末・液体などさまざまなタイプがあり、ライフスタイルに合わせて選ぶことができます。
ただし、摂りすぎるとお腹がゆるくなることがあるため、必ず適量を守りましょう。
また、成長期の子どもに与える場合は、大人用ではなく子ども用の商品を選ぶ、あるいは医師に相談することをおすすめします。
マグネシウム入りの入浴剤は、スポーツや入浴後のリフレッシュ習慣として取り入れる方も増えています。
親子で一緒に楽しみながら使えるのも、マグネシウム風呂の魅力の一つです。
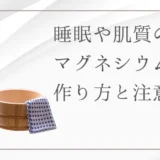 マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法
マグネシウム風呂の効果とは?疲労回復・美肌を目指す健康入浴法
生活習慣の工夫で吸収を高める
マグネシウムは、食生活や生活習慣を工夫することで、効率よく摂取できると考えられています。
ポイントの一つが「栄養素の組み合わせ」です。
マグネシウムはカルシウムやビタミンD、たんぱく質とともに摂ることが推奨されることがあるので、食事全体のバランスを意識すると良いでしょう。
たとえば、豆腐や納豆といった大豆製品に小魚や海藻を合わせ、日光浴でビタミンDを補うなど、和食の献立は自然と栄養バランスを取りやすいといわれています。
一方で、加工食品や清涼飲料、スナック菓子などに多く含まれるリン酸塩や砂糖、カフェインはマグネシウム摂取の妨げになると指摘されることも。
過度な摂取を控えることが望ましいでしょう。
また、休養や睡眠も健やかな生活に欠かせません。
夜更かしを避けて十分な睡眠をとることが、日々の栄養バランスを保つ上でも大切です。
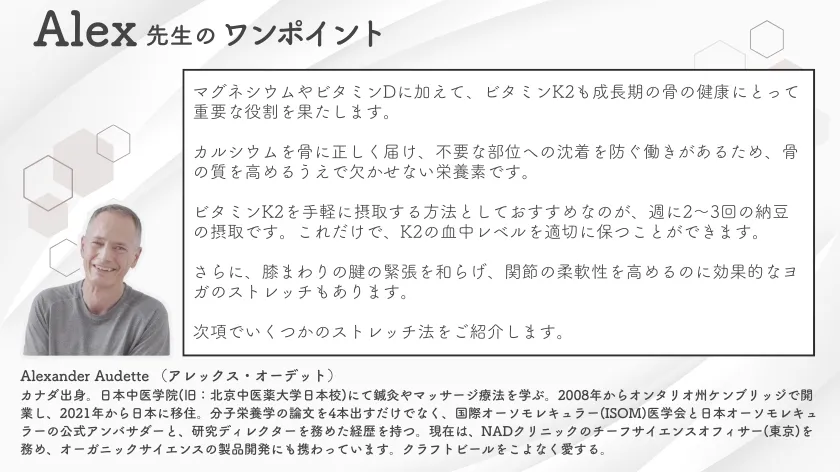
マグネシウムやビタミンDに加えて、ビタミンK2も成長期の骨の健康にとって重要な役割を果たします。カルシウムを骨に正しく届け、不要な部位への沈着を防ぐ働きがあるため、骨の質を高めるうえで欠かせない栄養素です。
ビタミンK2を手軽に摂取する方法としておすすめなのが、週に2〜3回の納豆の摂取です。これだけで、K2の血中レベルを適切に保つことができます。
さらに、膝まわりの腱の緊張を和らげ、関節の柔軟性を高めるのに効果的なヨガのストレッチもあります。次項でいくつかのストレッチ法をご紹介します。
膝まわりの腱の緊張を和らげるストレッチ
1.立ち膝で行うストレッチ

まずは床に立ち膝をし、腰に手をあてながら状態を軽く逸らします。
この時点で膝まわりの腱が伸びていると感じる方は、この状態を10~20秒ほどキープし、2~3セットほど繰り返しましょう。
決して無理をせず、まだ余裕がある方は次のステップに進んでみてください。

余裕がある方は、写真のように状態を逸らしながら、両手先を足のかかと部分へと伸ばします。こうすることで膝まわりの腱が伸びているのを感じられるはずです。
ポイントは、膝は床に対して90度の角度でまっすぐ立てたまま、腰を逸らせること。
腰が弱い方は無理をせず、気持ちいいと感じる程度で止めてください。

さらにしっかり膝まわりの腱にアプローチしたい方は、写真のように顔を上にあげ、体全体で膝まわりの腱を引っ張るイメージで状態を逸らします。
普段あまり使わない腱や筋肉にアプローチできるので、毎日の習慣にして、体の柔軟性の維持に努めると理想的です。
2.立ったまま行えるストレッチ

立ったまま片手で片足を持ち上げるだけでも、膝まわりの腱のストレッチになります。
手を使いながら足の甲を伸ばすイメージです。
足のつかみ方や角度などを色々と試しながら、お好みのポイントを探ってみましょう。
片足で立つとふらついてしまう方は、転倒リスク等を避けるため、無理せず何かにつかまりながら行ってください。
この手軽なストレッチ法は、自宅はもちろん外出先などでも実践できるのがメリットです。

マグネシウムの摂りすぎに注意が必要?

マグネシウムは成長期の骨や筋肉を支える大切なミネラルですが、「たくさん摂れば摂るほど良い」というわけではありません。
通常の食事から過剰に摂取する心配はほとんどありませんが、サプリメントや医薬品、マグネシウムを多く含む入浴剤を長期間使用する場合には注意が必要です。
特に過剰摂取で起こりやすいのが、下痢や腹部の不快感といった消化器系のトラブルです。
これは体が吸収しきれなかった分が腸内に残り、水分が引き込まれることで起こると考えられています。
また、腎機能が低下している人では排出がうまくいかず、高マグネシウム血症と呼ばれる状態になることがあり、注意が必要です。
では、どのくらいの量が目安になるのでしょうか。
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」では、成長期の子どもに必要なマグネシウム量は1日およそ200〜360mg程度、大人の場合は1日310〜380mg程度とされています。
大切なのは「不足を防ぐこと」と「摂りすぎないこと」のバランスです。
基本は食事から摂取し、必要に応じてサプリや入浴法を生活習慣の中で補助的に取り入れると安心です。
詳しくは「マグネシウムを摂りすぎるとどうなる?よくある症状と適量の目安」も参考にしてください。
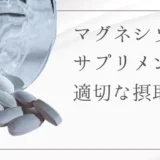 マグネシウムを摂りすぎるとどうなる?よくある症状と適量の目安
マグネシウムを摂りすぎるとどうなる?よくある症状と適量の目安
日常生活でできるオスグッド対策

オスグッド病は成長期によく見られるスポーツ障害ですが、日常生活の工夫によって膝への負担を減らし、体をいたわることが大切です。
ポイントは「膝にかかる負担を和らげること」と「日々の生活習慣を整えること」。
ストレッチや休養、アイシングといったセルフケアに加えて、栄養バランスの良い食事や十分な睡眠を心がけることが、健やかな成長を支える上で役立ちます。
ここからは、日常生活で意識したいポイントをご紹介します。
ストレッチ・休息・アイシング
オスグッド病のケアでは、太ももの筋肉をやわらかく保つことが大切とされています。
特に大腿四頭筋が硬くなると膝下に負担がかかりやすくなるため、日常的にストレッチを取り入れることが推奨されています。
たとえば、片脚を後ろに曲げてかかとをお尻に近づけるストレッチや、正座の姿勢から軽く体を後ろに倒すストレッチは、大腿部を伸ばす方法としてよく行われています。
また、痛みを感じるときは無理をせず休養をとることも大切です。
練習を休むことに抵抗を感じる子どもも少なくありませんが、体を休めることはコンディションを整える上で欠かせません。
さらに、膝に違和感や熱感があるときには、冷却(アイシング)を取り入れる場合もあります。
氷や保冷剤をタオルで包み、10〜15分ほど当てると一時的に冷やすことができます。
ストレッチ・休養・アイシングをバランスよく取り入れることで、膝への負担を和らげ、日常生活を快適に過ごすサポートにつながるでしょう。
食事と睡眠で回復力を高める
成長期の子どもが健やかにスポーツや日常生活を続けるためには、膝への負担を和らげる工夫に加えて、体をしっかり休めることや栄養バランスの良い食事が大切です。
食事面では、骨や筋肉の材料となるカルシウムやたんぱく質に加えて、さまざまな代謝に関わるマグネシウムなどのミネラルを意識して取り入れると安心です。
たとえば、牛乳や小魚、豆腐などのカルシウム源と、海藻やナッツ、玄米などのマグネシウムを含む食品を組み合わせると、バランスの良い食事になります。
また、運動後には肉や魚、大豆製品などからたんぱく質を補うことで、栄養面から日常のコンディション維持を意識できます。
さらに、“睡眠”も欠かせない要素です。
成長期には夜間の休養がとても大切で、規則正しい生活リズムを整えることが、心身の健康につながります。
夜更かしや睡眠不足は疲れを残しやすいため、毎日しっかり眠ることを意識しましょう。
親子で取り組むセルフケア
子どもは「少し痛くても練習を続けたい」と無理をしてしまうことがあります。
だからこそ、親子で一緒に体をいたわる工夫をする姿勢が大切です。
まずは、痛みや違和感が強いときは練習を休む勇気を持ちましょう。
子どもは「休むと仲間に迷惑をかける」「試合に出られなくなる」と不安に思うこともありますが、親が「あなたの健康が一番大事」と声をかけることで、安心して休養をとれるようになります。
ストレッチや冷却(アイシング)などのセルフケアも、親子で一緒に行うと習慣にしやすくなるでしょう。
寝る前の数分をストレッチの時間にしたり、練習後に一緒にアイシングを準備したりといった小さな工夫が、継続の力になります。
さらに、食事や睡眠の環境づくりも家庭でできる大切なサポートです。
成長期に必要な栄養を意識して整えたり、夜更かしを避けてしっかり休める環境をつくったりすることは、家庭ならではのサポートといえるでしょう。
オスグッド病に限らず、成長期の子どもの健康づくりは「家族で一緒に取り組む」ことが安心感につながり、子どもの心の支えにもなるのです。
まとめ|マグネシウムを活用してオスグッドを乗り越えよう!

オスグッド病は成長期の子どもに多く見られるスポーツ障害であり、日常生活の中では「休養」「ストレッチ」「栄養バランスのとれた食事」など、基本的な生活習慣を大切にすることが欠かせません。
特にマグネシウムは骨や筋肉のはたらきに関わるミネラルの一つで、海藻・大豆製品・ナッツ・玄米などの食品に含まれています。
普段の食事の中で意識して取り入れると、栄養バランスの改善につながるでしょう。
お子さんの成長期には、生活リズムを整え、家族で一緒に健康的な習慣を意識することが大切です。
本記事でご紹介した内容を参考に、毎日の生活に取り入れられる工夫を見つけてみてください。