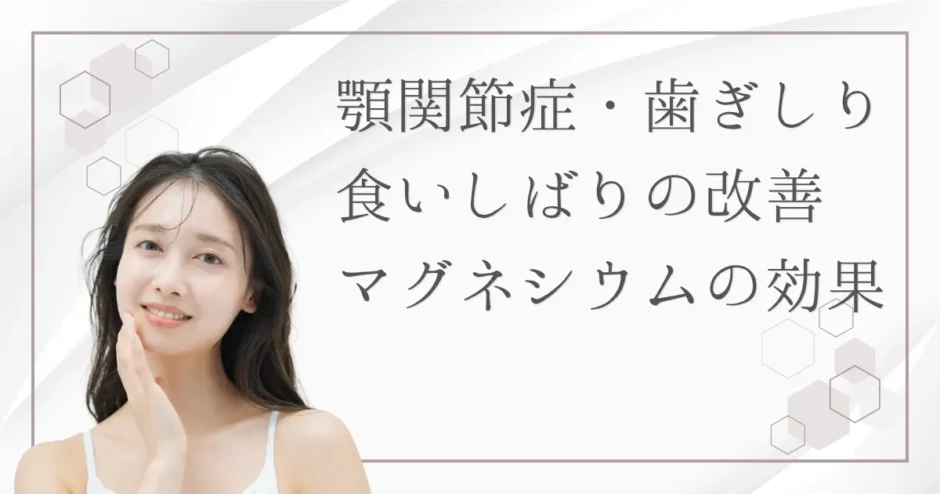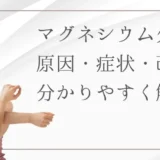朝、あごに違和感を覚えたり、寝ているあいだの歯ぎしりを指摘された経験はありませんか?
それは、顎関節症や食いしばりが関係しているかもしれません。
顎関節症や歯ぎしり・食いしばりは、あごの筋肉や神経の緊張が長く続くと起こりやすいといわれており、その背景にマグネシウム不足が関係している可能性も指摘されています。
本記事では、マグネシウムが顎関節症や歯ぎしり・食いしばりにもたらす効果やおすすめの摂取法について解説します。
マウスピースやマッサージを試しても歯ぎしりや食いしばりが改善しない方は、ぜひ参考にしてください。
顎関節症・歯ぎしり・食いしばりとは?

顎関節症は、口の開閉に関わる関節がうまく機能しなくなる障害で、歯ぎしりや食いしばりはその原因や悪化要因の一つです。
どの症状も、放置すれば日常生活に支障をきたすだけでなく、全身の不調へと広がるおそれがあります。
ここでは、顎関節症・歯ぎしり・食いしばりの主な原因と症状、放置した場合に起こるリスクについて解説します。
顎関節症の主な症状
顎関節症は、あごの関節や周囲の筋肉に異常が生じると発症するあごの疾患です。
顎関節症の主な症状には、次のようなものがあります。
- あご周辺やこめかみに重だるい違和感がある
- 口を大きく開けづらい、または開けると痛みが走る
- あごを動かすと「カクッ」「コリッ」と音が鳴る
- 食事中にあごが疲れやすく、噛む動作がつらい
- 症状が進むと頭痛や首・肩のこり、耳鳴りなど全身に不調が広がる
また、顎関節症は一度良くなっても再発するケースが多く、とくに歯ぎしりや食いしばりの癖がある人は、顎関節へ負担がかかりやすいため、悪化しやすい傾向があります。
参考:顎関節症、歯ぎしり・食いしばりでお悩みの方へ |青山バランスアップ治療院
歯ぎしり・食いしばりの原因
歯ぎしりや食いしばりは、主に次の3つが原因だといわれています。
- ストレス
- 睡眠の質の低下
- 筋肉の過度な緊張
歯ぎしりや食いしばりは「癖」と捉えられがちですが、実際には身体がストレスや疲労を発散しようとする無意識の反応でもあります。
また、デスクワークなどで長時間同じ姿勢を続ける人や、上下の歯を常に接触させる癖がある人も注意が必要です。
姿勢の崩れや咬み合わせのずれは、顎関節に負担をかける要因となります。
さらに、カフェインの摂り過ぎや喫煙、過度な緊張などの生活習慣も関係しており、複数の要因が重なって症状を引き起こすケースも多く見られます。
参考:顎関節症、歯ぎしり・食いしばりでお悩みの方へ |青山バランスアップ治療院
顎関節症・歯ぎしり・食いしばりを放置するとどうなる?
顎関節症・歯ぎしり・食いしばりを放置すると、あごの関節に慢性的な炎症が起こり、口の開閉障害や痛みが悪化するおそれがあります。
また、食事や会話といった日常動作に支障をきたすだけでなく、歯のすり減りや欠け、詰め物・被せ物の破損といった二次的なトラブルにもつながりかねません。
さらに、噛みしめによる筋肉の緊張は首や肩にも影響を及ぼし、慢性的な肩こりや頭痛、めまい、不眠などの全身症状を引き起こす場合もあります。
とくに女性は筋肉量が少ないため、あごへの負担が蓄積しやすく、症状が長引く傾向があるため注意が必要です。
早いうちにケアを取り入れてあごの緊張をやわらげると、症状の重症化を防げます。
参考:顎関節症、歯ぎしり・食いしばりでお悩みの方へ |青山バランスアップ治療院
マグネシウムは顎関節症や歯ぎしり・食いしばりにどんな効果がある?

近年では、マグネシウムが顎関節症や歯ぎしり・食いしばりのケアに効果的な栄養素として注目されています。
ここでは、マグネシウムの働きと顎関節症・歯ぎしり・食いしばりにどんな効果があるのかについて解説します。
筋肉のこわばりをゆるめ、あごの緊張をやわらげる
マグネシウムはカルシウムと連携して、筋肉の収縮と弛緩をコントロールする役割を担っており、両者のバランスが崩れると筋肉が硬直しやすくなります。
マグネシウムが不足すると筋肉が過剰に収縮したままになり、あごまわりの筋肉のこわばり、開口時の痛みや違和感が起こりやすくなります。
日常的にあごの緊張を感じやすい方は、筋肉を内側からサポートするためにもマグネシウムの意識的な補給が大切です。
マグネシウムを十分に摂取できると、筋肉は弛緩しやすくなり、顎関節や周辺の筋肉がリラックスした状態を保ちやすくなります。
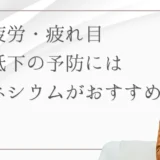 眼精疲労・疲れ目にはマグネシウムがおすすめ!視力の低下予防に効果的と言われる理由
眼精疲労・疲れ目にはマグネシウムがおすすめ!視力の低下予防に効果的と言われる理由
ストレスをやわらげ歯ぎしりや食いしばりを軽減する
マグネシウムは神経の興奮を抑え、ストレスをやわらげる作用を持つため、夜間の歯ぎしりや食いしばりの回数を減らす効果が期待できます。
また、マグネシウムのリラックス作用によって睡眠の質も向上するため、寝つきが悪い・眠りが浅いと感じる方にも効果的です。
ストレスや不安が続くと、自律神経のバランスが崩れ、無意識のうちに歯を噛みしめる動作が増えてしまいます。
体内のマグネシウム量が十分であれば、精神的な緊張がやわらぎ、リラックスしやすい状態を維持しやすくなります。
神経の興奮を抑えてリラックスしやすい状態をつくる
マグネシウムは、神経伝達物質のバランスを保ち、交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)の切り替えをスムーズにする働きがあります。
マグネシウムが不足すると、交感神経が優位な状態が続くため、体が常に緊張しているような感覚に陥り、筋肉のこわばりや睡眠中の歯ぎしりが起こりやすくなります。
神経の興奮を抑え、心身のリズムを整えるには、十分な量のマグネシウム摂取が欠かせません。
また、安定した神経状態の維持は、顎関節症や食いしばりの再発防止にもつながります。
歯科分野でも注目されるマグネシウムの働き
近年では、歯科医療の分野でも、マグネシウムの働きが注目されています。
顎関節症や歯ぎしりの治療では、マウスピースで歯を保護したり、理学療法で筋肉を調整したりする方法が一般的ですが、マグネシウムを取り入れるとこれらの治療をより効果的にサポートできるといわれています。
顎関節症や歯ぎしりの治療におけるマグネシウムの働きは次のとおりです。
- あごまわりのこわばりを軽減する
- 神経の興奮を落ち着かせる
- 治療中の不快感を減らし、回復を助ける
また、マグネシウムは血流を促す働きもあり、顎関節や周辺の筋肉に必要な酸素や栄養を届けやすくするサポートもします。
最近は、マグネシウムオイルやエプソムソルトを活用したリラックスケアを推奨する歯科医院も増えており、自宅で行えるセルフケアとしても広まりつつあります。
参考:エプソムクリームを100人に処方歯科クリニックで評価される理由|EPSOM&CO株式会社
歯ぎしり(ブラキシズム)に対しては、経口および経皮マグネシウム補給とあわせて、鍼治療を取り入れるケースが多く見られます。
鍼治療は、副作用の少ない部位特異的な抗炎症・鎮静・鎮痛療法であり、慢性的な筋緊張をやわらげ、睡眠の質を高める効果が期待できます。
私がカナダで臨床に携わっていた際も、この鍼治療を中心に据え、経皮・経口マグネシウム補給やほかの栄養療法と組み合わせることで、より良い結果を得てきました。
これらを組み合わせることで、心身のバランスを整え、自らの回復力を引き出すサポートになります。
マグネシウムを効果的に摂るなら「経皮吸収」がおすすめ

マグネシウムの摂取方法には、食事やサプリメントなどの口から摂る「経口摂取」とオイルや入浴剤など皮膚から直接取り入れる「経皮吸収」があり、体質やケアの目的によっておすすめの方法が分かれます。
顎関節症・歯ぎしり・食いしばりのケアを目的とする際は、経皮吸収がおすすめです。
経皮吸収は、マグネシウムを皮膚に直接取り込むため吸収効率が高く、体に負担をかけずに摂取できるのが特徴です。
ここでは、経皮吸収を中心にマグネシウムを効率よく摂る方法について解説します。
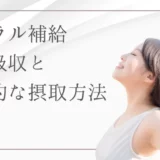 経皮吸収とは?肌から成分が吸収される仕組みを分かりやすく解説
経皮吸収とは?肌から成分が吸収される仕組みを分かりやすく解説
エプソムソルト入浴で全身から吸収
エプソムソルトは「硫酸マグネシウム」を主成分とする入浴剤で、欧米では古くから疲労回復やリラクゼーション目的で使われています。
お湯に溶かして入浴すると、皮膚を通してマグネシウムが全身に吸収され、筋肉の緊張をやわらげて血行を促進する効果があるため、筋肉のこわばりや冷え、だるさを感じる方におすすめです。
あごや肩の筋肉が硬くなっているときにも、エプソムソルトは効果的で、入浴後に顔まわりがすっきり軽く感じられる場合があります。
また、就寝前に入浴すると副交感神経が優位になり、リラックスしやすくなるため、歯ぎしりや食いしばり予防のナイトルーティンとしても取り入れやすい方法です。
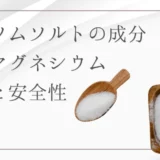 エプソムソルトの成分とは?硫酸マグネシウムの効果と安全性を徹底解説!
エプソムソルトの成分とは?硫酸マグネシウムの効果と安全性を徹底解説!
マグネシウムオイルやクリームで筋肉をリラックス
マグネシウムオイルやクリームは、気になる部分をピンポイントでケアできるのが特徴です。
とくに、あごの筋肉(咬筋)やこめかみ、首まわりなど、緊張が強く出やすい部分に直接塗布すると効果的です。
塗布後に軽くマッサージを行うと、皮膚表面からマグネシウムが吸収され、筋肉の緊張をやわらげて血行を促します。
「夜、歯ぎしりをしてしまう」「朝起きるとあごが疲れている」と感じる方は、寝る前のフェイスマッサージと併用すると、翌朝のすっきり感を実感しやすいでしょう。
さらに、神経の高ぶりを落ち着かせる作用もあるため、日中のストレス緩和や就寝前のリラックスケアにも適しています。
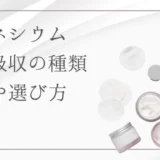 マグネシムバーム・クリーム・スプレーの違いとは?目的別おすすめの使い方を解説
マグネシムバーム・クリーム・スプレーの違いとは?目的別おすすめの使い方を解説
サプリメントや食事との併用で吸収効率を高める
経皮吸収は非常に効率的な方法ですが、経口摂取による内側からのサポートも欠かせません。
マグネシウムを多く含む食材を日常的に取り入れながら、マグネシウムオイルやエプソムソルト入浴を併用すると、内外両面からバランスよく補えます。
また、吸収効率を高めたい場合は、カルシウムやビタミンB群、ビタミンDなどを一緒に摂るのもおすすめです。
サプリメントを選ぶ際は、1日の推奨量(成人で約300〜400mg)を守り、過剰摂取にならないよう注意しましょう。
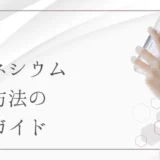 マグネシウムの効率的な摂取方法3選|1日の推奨量と不足チェック
マグネシウムの効率的な摂取方法3選|1日の推奨量と不足チェック

マグネシウムを活用したセルフケアで顎関節症・歯ぎしり・食いしばり対策

マグネシウムは、サプリメントや入浴などで摂取するだけでなく、セルフケアの一部として取り入れる方法でも顎関節症や歯ぎしりの緩和に役立ちます。
また、マグネシウムケアを日常の生活習慣(姿勢・睡眠・ストレス対策など)と組み合わせると、より高い相乗効果が得られます。
ここでは、自宅でも簡単に実践できるマグネシウムを活用したセルフケア方法を紹介します。
マウスピースとマグネシウムケアであごの負担をやわらげる
歯ぎしりや食いしばりの予防には、歯を保護するためのマウスピースが使用されるケースが多いですが、根本的な筋肉の緊張までは緩和しにくい場合があります。
そこでおすすめなのが、マグネシウムオイルとの併用です。
マグネシウムオイルを手に取り、あごの筋肉(咬筋)やこめかみ、首の付け根などに優しくなじませながらマッサージすると、筋肉がゆるみ、寝ているあいだの噛みしめを防ぎやすくなります。
また、朝起きたときにあごのだるさが残っている場合は、温かいタオルで軽く温めてからマッサージするとより効果的です。
マグネシウム入浴でしっかり眠る習慣を意識する
エプソムソルトなどのマグネシウム入浴剤は、全身の筋肉を優しくほぐし、血行を促進する効果があります。
40℃前後のぬるめのお湯にエプソムソルトを入れ、15〜20分程度ゆっくり浸かるのがおすすめです。
入浴中は深呼吸を意識し、肩や首の力を抜いてリラックスすると、副交感神経が優位になりやすく心身が落ち着き、夜間の歯ぎしりや食いしばりの予防にもつながります。
また、寝る直前に入浴すると体温が一時的に上がり、その後の自然な体温低下によって眠気が促されます。
入浴後は水分をしっかり補給し、スマートフォンなどの刺激を避けて穏やかに過ごしましょう。
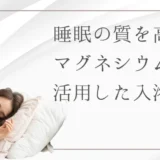 お風呂の入り方で睡眠の質が上がる!マグネシウムを利用した快適入浴法
お風呂の入り方で睡眠の質が上がる!マグネシウムを利用した快適入浴法
セルフケアで改善しない場合は歯科医に相談する
マグネシウムを取り入れても、あごの痛みや口の開け閉めがしづらい場合は、歯科医へ相談しましょう。
顎関節症や歯ぎしりは、噛み合わせのずれ、ストレス、筋肉や骨格のバランスなど、複数の要因が絡み合って起こります。
「マッサージしてもすぐにこわばる」「音が鳴って痛い」「口が開けにくい」といった症状がある場合は、自己判断で放置せず、早めに歯科医を受診するとよいでしょう。
 マグネシウムで心と体を整える|疲労・ストレス・不眠を改善するセルフケア法
マグネシウムで心と体を整える|疲労・ストレス・不眠を改善するセルフケア法
まとめ|マグネシウムを取り入れて顎関節症・歯ぎしり・食いしばりを緩和しよう

顎関節症や歯ぎしり・食いしばりは、多くの場合「無意識の緊張」から生まれます。
そうした「緊張」をやわらげるために役立つのが、マグネシウムです。
顎関節症や歯ぎしり・食いしばりは、放置すると全身の不調にもつながる場合がありますが、日常的なマグネシウムケアで十分に軽減が期待できます。
マグネシウムを味方に、体の内側から緊張をゆるめる習慣を取り入れましょう。