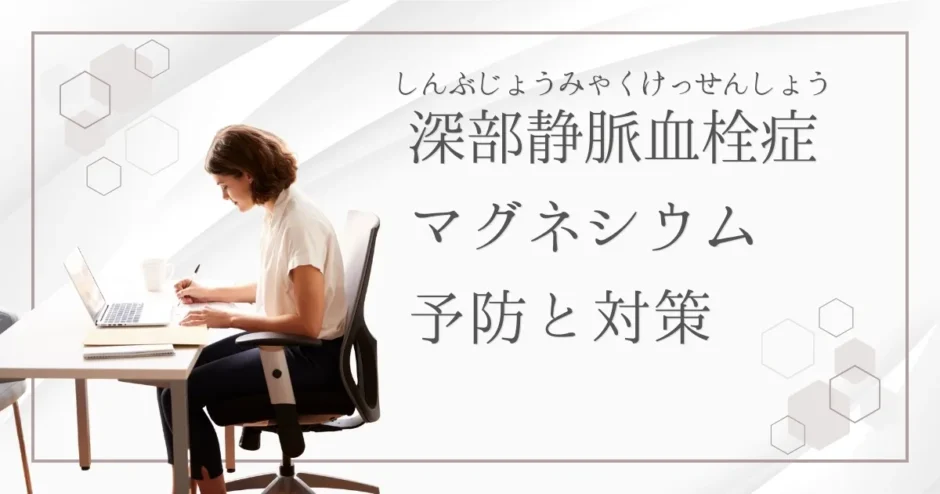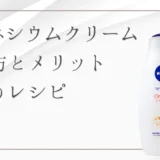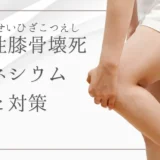長時間のフライトやデスクワークのあとに、足のむくみやだるさを感じたことはありませんか?
実はその感覚の裏には、「深部静脈血栓症(DVT)」と呼ばれる病気が潜んでいる可能性があります。
深部静脈血栓症は、血管の中に血のかたまり(血栓)ができて血流が妨げられる状態で、時には命に関わる「肺塞栓症」に発展することも。
こうしたリスクに対応するには、血流を滞らせない工夫が必要ですが、最近では栄養面からのアプローチにも注目が集まっています。
特に、体内の酵素反応や神経・筋肉の働きに関与するミネラルである「マグネシウム」が、血管の健康維持と関連があるのではないかとする研究や報告も見られるようになってきました。
マグネシウムは血流や循環系に関係するとされる重要なミネラルの一つで、栄養学的な観点から「血栓ができにくい体づくり」に貢献する可能性が示唆されています(ただし、これはあくまでも補助的な関係であり、医学的な効果を保証するものではありません。)。
今回は、深部静脈血栓症の基礎知識と併せ、マグネシウムが体内で果たす役割や、血流に配慮した日常生活の工夫についてわかりやすく解説します。
生活の中で取り入れやすい対策を知ることで、血管トラブルのリスク低減につながるヒントが見つかるかもしれません。
深部静脈血栓症(DVT)とは?

「エコノミークラス症候群」とも呼ばれる深部静脈血栓症は、長時間同じ姿勢でいることで脚の深い静脈に血栓(血のかたまり)ができ、血流が妨げられる状態を指します。
初期には自覚しにくいケースも多く、気付いた時には肺塞栓症など重大な症状につながっていることも。
この疾患は、一見すると単なるむくみや疲労のように思える症状から始まることが多いため、日頃からその特徴やリスクを正しく知っておくことが重要です。
特にデスクワークなど座りっぱなしの時間が長い人や、術後の安静が必要な方は、深部静脈血栓症を未然に防ぐための生活上の工夫が求められます。
まずは、深部静脈血栓症の原因や初期症状などの基本を、わかりやすく解説します。
深部静脈血栓症はどんな病気?
深部静脈血栓症(DVT:Deep Vein Thrombosis)は、脚の深部にある静脈に血栓ができることで、血流が妨げられる状態を指します。
主にふくらはぎや太ももなど、体の深い部分の静脈で発生しやすく、症状に気付きにくいまま進行することも少なくありません。
初期段階では「足がむくんでいるだけ」「少しだるいだけ」と感じる程度のこともありますが、血栓が剥がれて血流に乗って肺に到達すると、肺塞栓症(肺血栓塞栓症)という命に関わる重大な状態を引き起こすリスクも。
そのため、以下のような症状が見られる場合には早めに対応することが大切です。
- 片足だけが異常にむくむ
- ふくらはぎや太ももが痛む、張る感じがする
- 足が熱っぽく赤くなる
- 歩くと痛みが増す、つっぱる感覚がある
特に、症状が急激に悪化する場合や呼吸が苦しくなるような感覚がある場合は、医療機関での早急な対応が必要です。
日常の中では「ただの疲れ」や「長時間座っていたからかな」と見過ごされがちですが、静かに進行するタイプの血管トラブルとして、深部静脈血栓症の存在を知っておくことが予防の第一歩になります。
主な原因とリスク要因
深部静脈血栓症は、血流の停滞、血管内皮の損傷、血液の凝固亢進などが複合的に重なることで発症するとされています。
特に、以下のような要因が重なると、血栓ができやすい状態になると考えられています。
| リスク要因 | 内容 |
|---|---|
| 長時間同じ姿勢で過ごす | 飛行機やデスクワークなどで足を動かさない状態が続くと血流が滞りやすくなる |
| 手術・外傷後の安静 | 特に下肢・骨盤周辺の手術後は血栓形成のリスクが高まる |
| 加齢 | 血管の柔軟性が低下し、血流が停滞しやすくなる傾向 |
| 肥満 | 静脈への圧力が増し、血流が悪くなることでリスクが高まる |
| 脱水状態 | 血液の粘度が上がり、血栓ができやすい状態になる可能性がある |
| 喫煙習慣 | 血管収縮や血液の粘性上昇などが報告されており、血流に悪影響を与えることがある |
| ホルモン治療・経口避妊薬の使用 | 一部のホルモン製剤には血液凝固の作用があり、体質によりリスクが上がる場合がある |
| 妊娠・出産 | 骨盤内圧の上昇や血液量の変化により、血栓ができやすい状態になる |
| 基礎疾患の存在 | がん、心疾患、糖尿病、自己免疫疾患などがあると、血栓リスクが上昇する可能性がある |
| 遺伝的素因 | 先天的な血液凝固異常を持つ人は、DVTを発症しやすい傾向がある |
これらのリスク要因は単独ではなく、複数が重なることで発症リスクが高まると考えられています。
早めに予防・対策するためにも、生活環境や健康状態と照らし合わせ、自分にあてはまる項目がないかチェックしてみましょう。
初期症状に注意
深部静脈血栓症は、初期にははっきりとした症状が現れにくく、気付かれにくい病気です。
そのため、「ただのむくみかな?」「運動不足で足がだるいだけかも?」と見過ごしてしまうケースも少なくありません。
以下のようなサインが見られる場合は、血流に異常が起きている可能性があるので注意が必要です。
| 症状の特徴 | 主なチェックポイント |
|---|---|
| ふくらはぎの腫れ | 特に片足だけが明らかにむくんでいる場合は要注意 |
| ふくらはぎの痛み | 歩行時や圧迫時にピリピリと痛む、つっぱるような違和感がある |
| 熱感・赤み | 足が熱を帯びている、皮膚が赤く変色しているように見える |
| だるさ・重さ | 足が鉛のように重く感じる、動かすのがつらい |
| 片足だけ症状が出る | 両足ではなく、左右どちらか片側だけに異常が出る場合が多い |
これらの症状は、軽度のうちは日常生活に大きな支障をきたさないこともありますが、放置すると肺塞栓症など深刻な状態に発展する可能性もあります。
「いつもと違う」と感じた時は無理をせず、早めに医療機関で相談してみましょう。
特に長時間の移動後や、リスク要因がある方は、注意深く観察することが大切です。
マグネシウムの働きと血液循環の関係

深部静脈血栓症を予防する上で重要なポイントの一つが、血液の流れを滞らせないことです。
血流がスムーズに保たれることで、血栓が形成されにくい状態が維持されやすくなると考えられています。
そこで活用したいのが、血液循環を良好な状態で維持するミネラルの一つとして近年注目されている「マグネシウム」です。
マグネシウムは、筋肉や神経の機能をはじめ、体内の多くの酵素反応に関与する必須栄養素の一つであり、血管の健康や血液の状態にも間接的に関与する可能性があるとされているためです。
ここからは、マグネシウムがどのような働きを持ち、血液循環との関係においてどのように関わっているのかを、栄養学の視点から解説します。
ただし、あくまで補助的な要素としてであり、マグネシウムの摂取が深部静脈血栓症の発症を防ぐことを保証するものではないことをご留意ください。
マグネシウムの働き
マグネシウムは、私たちの体にとって欠かせない必須ミネラルの一つで、800以上の酵素反応に関与しているとされています。
筋肉の収縮と弛緩、神経伝達、エネルギー代謝、体温や血圧の調整など、さまざまな生理機能をサポートする重要な栄養素です。
中でも、血管や血液の健康との関わりに注目が集まっています。
マグネシウムは、以下のような働きを持つとする報告があります。
- 血管のしなやかさを保つ…血管平滑筋の弛緩を助け、血圧や血流の安定に関与する可能性がある
- 血小板の活性を調整する…血液が過剰に凝固しないよう、血小板の働きを緩やかに調整するとする報告がある
- 炎症反応に関与する…慢性的な炎症を引き起こすサイトカインの過剰な産生を抑える働きがある可能性がある
- ストレスホルモンに関与する…ストレス時に分泌されるホルモンの反応を緩和し、自律神経の安定に寄与することが示唆されている
これらの働きは、血液が過度に固まるのを防ぐための“体の自然な調整機能”の一部と考えられており、マグネシウムはそのバランスを支える栄養素として位置づけられています。
マグネシウム不足とDVTのリスクの関係性
マグネシウムは、現代人の多くが不足しやすい栄養素でもあります。
特に加工食品の摂取が多く、野菜や海藻、豆類などの摂取が不足しがちな食生活では、知らないうちにマグネシウムが不足しているケースも少なくありません。
マグネシウムが不足した状態が続くと、以下のような身体の変化が起こる可能性があると報告されています。
- 血液凝固のバランスの乱れ…血小板の働きが活性化しやすくなり、血液が固まりやすくなるとされることがある
- 血管の収縮傾向…マグネシウムが不足すると血管が収縮しやすくなり、末梢血流が滞りやすくなる可能性がある
- 炎症反応の促進…慢性的な炎症を抑える調整機能が弱まり、血管内で炎症性の変化が起きやすくなるとする研究もある
これらの現象は、深部静脈血栓症の発症要因として知られる「血液の凝固」「血流の停滞」「血管内皮の損傷」という三つのリスク要素と関係しており、マグネシウム不足が間接的に影響を及ぼす可能性があると指摘されています。
ただし、マグネシウム不足だけが深部静脈血栓症の原因になるわけではなく、生活習慣、体質、既往症など複数の要素が重なって発症リスクが高まることを理解しておきましょう。
マグネシウムが不足するとどうなる?
マグネシウムが慢性的に不足すると、全身のバランスに影響を及ぼす可能性があるとされています。
特に以下のような点で、体調の変化や血流環境に関与する可能性が報告されています。
- 血圧の上昇傾向…血管の収縮が強まりやすくなり、結果として血圧が不安定になることがある
- 動脈硬化の進行しやすさ…血管の柔軟性が低下し、動脈の硬化が進みやすくなるリスクがあるとする報告がある
- 血液の粘度上昇…血液がドロドロとした状態になり、流れが悪くなる可能性がある
- ストレス耐性の低下…精神的なストレスに対する反応が強まり、自律神経のバランスが乱れやすくなるとされている
- 睡眠の質の低下…睡眠に関わる神経伝達物質の生成にマグネシウムが関与しているとされ、不足すると睡眠の質に影響が出る可能性がある
これらの要因が組み合わさると、血流が悪化しやすくなり、深部静脈血栓症のリスクが高まる可能性があると指摘されています。
血管の健康を保つために、栄養状態の見直しも一つの視点として取り入れましょう。

深部静脈血栓症を予防するために

深部静脈血栓症は、初期には自覚しにくいにもかかわらず、重篤化すると命に関わるリスクもあるため注意が必要な疾患です。
とはいえ、必ずしも予防が難しい疾患というわけではなく、日々の生活習慣の工夫によってリスクを軽減できる可能性があると言われています。
血流を滞らせないようにすること、水分をしっかりとること、筋肉を適度に動かすこと、そして必要な栄養素を意識して摂ることは、いずれも血栓ができにくい環境を整えるために役立つ習慣として注目されています。
ここからは、マグネシウムを含む食生活の見直しや、座りっぱなしの時間が多い方でも日常に取り入れやすい運動・休息・セルフケアのポイントを具体的にご紹介します。
こまめな水分補給を心掛けよう
血流をスムーズに保つためには、水分補給が非常に大切な習慣です。
体内の水分量が不足すると、血液の粘度が高まり、流れが悪くなる傾向があります。
これにより、血栓ができやすい状態を招く可能性があるため、日常的にこまめに水分をとることが重要です。
特に以下のような状況では、意識して水分を補うよう心掛けましょう。
- 飛行機やバス、車などでの長時間移動中
- オフィスや在宅勤務で座りっぱなしになる日
- エアコンで乾燥した環境に長くいるとき
- 起床直後や入浴後、就寝前など、体から水分が失われやすいタイミング
また、水分補給の際は次のポイントを意識するのがおすすめです。
- 一度に大量ではなく、1回200ml程度をこまめにとる
- カフェインやアルコールは利尿作用があるため、水や麦茶、白湯などを中心に
- 喉が渇く前に飲むことを意識する
血液の循環を支える土台として、水分補給はもっとも基本的な要素の一つです。
無理のない範囲で、こまめに水分をとる習慣を日常生活に取り入れてみましょう。
食習慣を見直そう
深部静脈血栓症の予防を考える上では、血流や血管の健康を栄養面からサポートする意識も大切です。
私たちの健康を支えるミネラルであるマグネシウムを、できるだけ日々の食事から摂取するよう意識したいですよね。
以下は、マグネシウムを多く含む食品の一例です。
- 海藻類…わかめ、ひじき、昆布 など
- 豆類…大豆、納豆、黒豆、おから など
- ナッツ類…かぼちゃの種、アーモンド、カシューナッツ、くるみ など
- 魚介類…いわし、さば、しらす、あさり など
- 野菜類…ほうれん草、小松菜、ブロッコリー など
- 全粒穀物…玄米、雑穀米、オートミール など
栄養はすぐに目に見える変化をもたらすものではありませんが、健康的な体づくりを支える大切な要素の一つです。
無理なく続けられる食習慣から、体の内側からのケアを意識してみましょう。
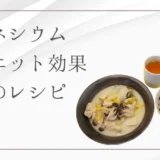 【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選
【料理研究家監修】マグネシウムたっぷりのオリジナルレシピ4選&ヘルシーメニュー5選
運動習慣を見直そう
長時間同じ姿勢で過ごすことが多い現代の生活では、血流が滞りやすく、下半身に血栓ができるリスクが高まりやすいとされています。
特にデスクワークや長距離移動では、足の筋肉をほとんど動かさないまま何時間も過ごすことが珍しくありません。
そんな日常において、ちょっとした動きをこまめに取り入れることが、血流促進の一助となると考えられています。
| 日常に取り入れやすい軽い運動の例 | |
| デスクワーク中 | 足首を回す・つま先を上下に動かす・椅子に座ったまま脚を伸ばすなど |
| 移動中 | 立ち上がって軽くストレッチ・トイレや通路まで歩く |
| 日常生活中 | エレベーターではなく階段を使う・家事中に足踏みを入れる |
| 就寝前や入浴後 | ふくらはぎや太もものストレッチ、軽いスクワットなどを無理のない範囲で行う |
定期的な運動のポイント
- 1日5〜10分でも良いので、下半身を意識的に動かすことが大切
- 可能であれば1時間に1回は立ち上がって軽く体を動かす
- ウォーキングや軽い散歩もおすすめ(無理のないペースで)
運動は血流を促すだけでなく、筋肉のポンプ作用を活用して、静脈の血液を心臓に戻す働きも支えるとされています。
無理のない範囲で、今の生活に合った動きを意識することが、日々の体調管理やDVTリスク軽減に役立つ一歩になるでしょう。
睡眠習慣を見直そう
睡眠は、心身の回復だけでなく、血液循環や自律神経のバランスを整える上でも重要な生活習慣の一つとされています。
睡眠不足が続いたり、逆に横になったまま動かない時間が長くなったりすると、血流が滞りやすくなることがあり、間接的に血栓リスクと関連する可能性も。
特に術後や出産後などで長期間の安静が必要なときは、医師の指導のもとでできるだけ早期に体を動かす工夫を取り入れることが大切です。
睡眠と血流ケアのポイント
- 日中の活動量を確保して、夜に自然な眠気が来るリズムをつくる
- 睡眠前にスマートフォンや強い光を避ける(ブルーライト対策)
- 寝る前の軽いストレッチや深呼吸で副交感神経を優位にする
また、質の良い睡眠はストレス緩和にもつながり、自律神経が整いやすくなるとも言われています。
自律神経のバランスが崩れると、血管の収縮や血流の乱れに影響を及ぼす可能性があるため、睡眠環境を整えることもDVT予防の一環として意識しておきましょう。
体をケアする習慣をつけよう
日々のちょっとしたセルフケアが、血流の滞りを防ぐ手助けになることがあります。
特にふくらはぎや太ももなど、下半身の筋肉をやさしく刺激するようなケアは、静脈の流れをサポートする要素の一つとされています。
また、ストレスや緊張が続くと自律神経のバランスが乱れやすくなり、それが血管の収縮などに影響を与えることもあるため、心と体をほぐす習慣を日常に取り入れることも大切です。
| 体のケアに取り入れたい習慣例 | |
| 温浴習慣 | ぬるめのお湯にゆったり浸かることで、全身の血行促進とリラックスをサポート |
| マグネシウム入りの入浴剤 | 肌からマグネシウムを取り入れるという観点で注目されており、リラックスタイムに活用される例も |
| セルフマッサージ | 足首からふくらはぎへ向かって優しくマッサージすることで、筋肉をほぐし、血流を促す助けに |
| ストレッチ | 寝る前や起床後に太ももやふくらはぎを中心としたストレッチで、可動域を広げ筋肉をゆるめる |
無理のない範囲で、こうした習慣を「毎日のルーティン」として取り入れることで、自分の体の状態に気付くきっかけにもなるでしょう。
ただし、あくまで体調に合わせてこれらを実践し、痛みや不調があるときは無理をせず専門家に相談するのがおすすめです。
弾性ストッキングの活用
弾性ストッキング(医療用着圧ソックス)は、足に段階的な圧力を加えることで、血液が下半身に滞りにくくなるようサポートする目的で使用される製品です。
特に、長時間座り続けることが避けられない飛行機での移動中や、オフィスでのデスクワークが続く場合、術後や出産後などで安静が必要な期間などに活用されることがあります。
医療現場でも、深部静脈血栓症の予防策の一環として、弾性ストッキングの着用が推奨されるケースがあります。
足首から太ももにかけて段階的に圧がかかる設計になっており、静脈の血流を助けるよう考慮されているのが特徴です。
きつすぎる製品を選んでしまうと逆に血流を妨げる可能性があるため、自分に合ったサイズを選ぶことが大切です。
なお、初めて使用する方や、高血圧・皮膚疾患などの持病がある方は、医師や看護師などの医療従事者に相談の上で取り入れることをおすすめします。
また、使用中にかゆみや圧迫感が強く現れる場合には、無理をせず使用を中止しましょう。
弾性ストッキングはあくまで補助的な手段であり、適度な運動や水分補給と組み合わせることで、より自然に血流を整える生活習慣づくりにつながります。
安全に、無理なく、日常に取り入れていくことが大切です。
薬剤の活用
深部静脈血栓症のリスクが高いと判断された場合、医療機関では血液を固まりにくくする薬剤、いわゆる抗凝固薬が処方されることがあります。
これは、既に血栓ができていたり、その可能性があったりする方、あるいは手術後や長期の安静が避けられない方などに対して、必要に応じて用いられる治療の一環です。
抗凝固薬にはいくつかの種類があり、経口薬や注射薬など、使用方法や作用時間に違いがあります。
いずれの薬も、血液の流れを妨げないようにサポートするのが目的ですが、その分、出血しやすくなる副作用があるため、医師の指導のもとで正しく使用することが大前提です。
自己判断での使用や、市販の健康食品を代替的に使用することは推奨されていません。
血栓リスクが高いとされた場合には、まずは信頼できる医療機関で適切な診断と処方を受けることが重要です。
薬剤の使用はあくまでも医師の治療計画の一部であるという認識を持ち、自己管理と合わせて安全に進めましょう。
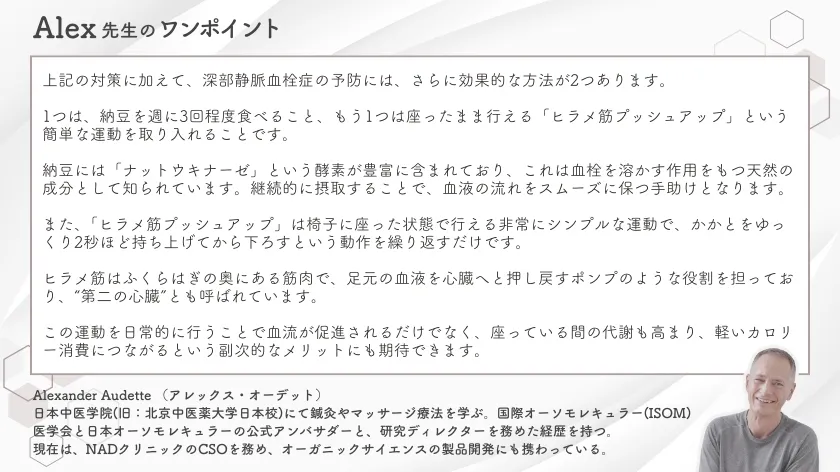
上記の対策に加えて、深部静脈血栓症の予防には、さらに効果的な方法が2つあります。1つは、納豆を週に3回程度食べること、もう1つは座ったまま行える「ヒラメ筋プッシュアップ」という簡単な運動を取り入れることです。
納豆には「ナットウキナーゼ」という酵素が豊富に含まれており、これは血栓を溶かす作用をもつ天然の成分として知られています。継続的に摂取することで、血液の流れをスムーズに保つ手助けとなります。
また、「ヒラメ筋プッシュアップ」は椅子に座った状態で行える非常にシンプルな運動で、かかとをゆっくり2秒ほど持ち上げてから下ろすという動作を繰り返すだけです。
ヒラメ筋はふくらはぎの奥にある筋肉で、足元の血液を心臓へと押し戻すポンプのような役割を担っており、“第二の心臓”とも呼ばれています。
この運動を日常的に行うことで血流が促進されるだけでなく、座っている間の代謝も高まり、軽いカロリー消費につながるという副次的なメリットにも期待できます。
まとめ|血栓リスクの少ない体づくりを

深部静脈血栓症は、初期段階では自覚症状が乏しい疾患です。
だからこそ、日々の生活の中で血流や血管の健康に配慮した習慣を意識することが、結果的に体全体のコンディションを守ることにつながります。
マグネシウムを含む食品を食生活に取り入れ、こまめな水分補給や軽い運動を習慣化することは、血流を保ちやすくするための一助になると考えられています。
また、入浴やストレッチ、弾性ストッキングの活用など、身近なセルフケアを取り入れることも、体への負担を軽減する工夫の一つです。
何より大切なのは、「今できること」から少しずつ取り入れていくこと。
完璧を目指す必要はありませんが、体に配慮した行動を積み重ねることで、自分の健康状態に対する意識が高まり、将来に向けた安心にもつながるはずです。
日常生活の中でできる範囲から、「血栓リスクの少ない体づくり」を意識してみませんか?