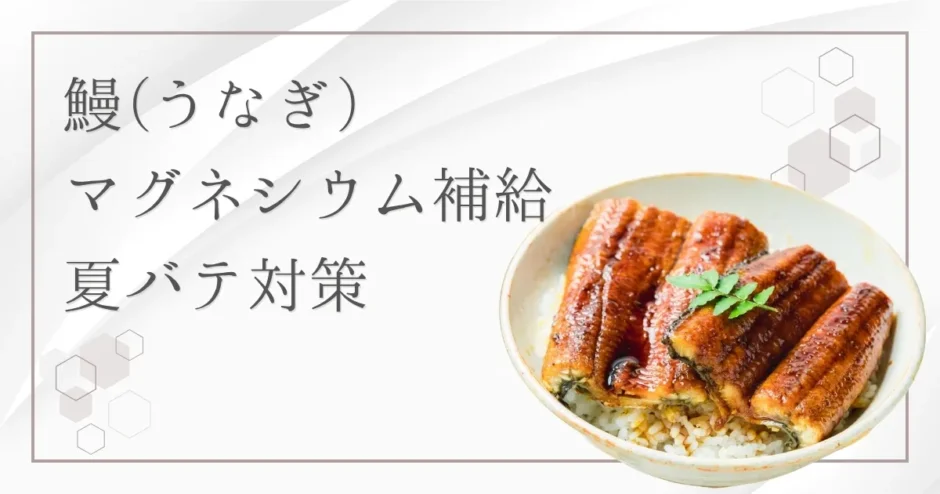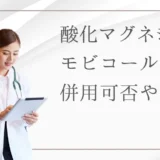暑さが本格化する季節になると、なんとなく体のだるさを感じたり、食欲が出なかったりといった「夏バテ」の症状に悩まされる方も多いのではないでしょうか。
近年は特に夏の猛暑が著しいため、エアコンに頼りっぱなしの生活や冷たい飲み物の摂り過ぎから、体内のミネラルバランスが崩れがちです。
特に注目したいのが、心身の健康をサポートする「マグネシウム」の働きです。
夏バテ予防にも寄与するマグネシウムは、発汗やストレスなどで失われやすいミネラルの一つでもあります。
実は、夏場に鰻を食べる習慣も、鰻にはマグネシウムをはじめとするさまざまなミネラルや栄養素が含まれているから。
土用の丑の日に鰻を食べるという風習は、日本人にとって馴染み深いものですが、実は理にかなった健康法なのです。
今回は、鰻に含まれる栄養素と夏バテとの関係、鰻を賢く食べる方法まで詳しく解説します。
夏バテとマグネシウムの関係

夏バテは水分不足やミネラル不足、自律神経の異常などさまざまな原因で起こる症状ですが、実はマグネシウムとも深く関わっています。
はじめに、夏バテとマグネシウムの関係について見ていきましょう。
マグネシウムの役割とは?
マグネシウムは、私たちの体内にある必須ミネラルの一つで、筋肉の収縮、神経伝達、エネルギー産生、酵素の活性化など、800以上の生理機能に関与しています。
心臓を安定的に動かすにも、体温を適切に調節するにも、マグネシウムの働きなしには成り立ちません。
特に夏は汗をかくことでナトリウムやカリウムとともに、マグネシウムも失われやすく、体内の健康バランスが崩れやすくなります。
マグネシウムや各種栄養素を補うために、栄養バランスが整った食事をしっかりと摂ったり、夏はミネラルが豊富な食事を心掛けたりなど、食事を工夫すること大切です。
夏バテの仕組み
そもそも夏バテとは、暑さや湿度の高さによって自律神経が乱れ、体の調整機能がうまく働かなくなる状態を指します。
主な症状として、食欲不振、倦怠感、めまい、睡眠障害、集中力の低下などがあげられます。
ひどい場合は熱中症や免疫力の低下にもつながる可能性があるため、十分な注意が必要です。
また、夏バテの症状の背景には、マグネシウム不足が影響している可能性があることも留意しましょう。
特に現代人のライフスタイルは、マグネシウムが不足しやすいとされています。
海藻や大豆製品、玄米など、昔ながらの日本食を代表する食材にはマグネシウムが豊富に含まれていますが、近代は食の欧米化や経済状況の変化などから、マグネシウム含有量が少ない加工食品やファーストフード、外食などを頼る人が増えました。
また、ミネラルを豊富に含む硬水が多く湧き出る欧米と異なり、日本の土壌はミネラルが少ない軟水がほとんどです。
ですから、日本人は特にマグネシウムを意識的に摂取する必要があります。
マグネシウムは、ストレスに対抗するホルモンの合成にも関わっており、メンタルバランスを整える上でも重要な役割を果たすので、不足すると心身のコンディションやパフォーマンスが低下する可能性があります。
夏の暑さに負けない体力作りの一環として、マグネシウムの積極的な補給も視野に入れましょう。
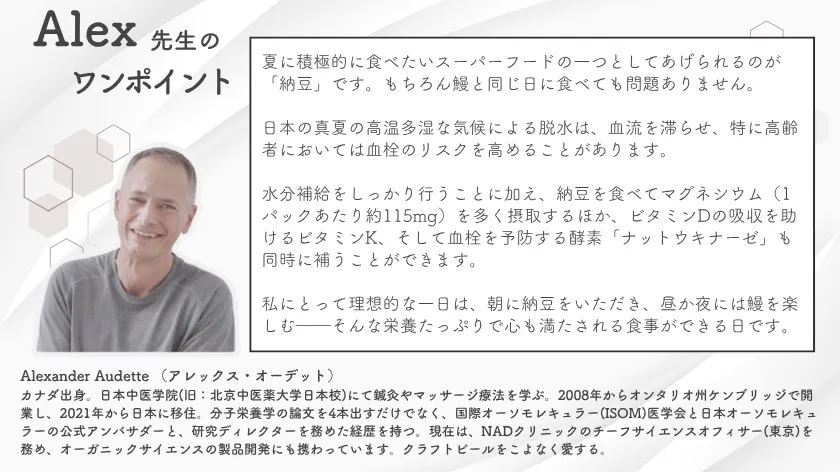
夏に積極的に食べたいスーパーフードの一つとしてあげられるのが「納豆」です。もちろん鰻と同じ日に食べても問題ありません。
日本の真夏の高温多湿な気候による脱水は、血流を滞らせ、特に高齢者においては血栓のリスクを高めることがあります。水分補給をしっかり行うことに加え、納豆を食べてマグネシウム(1パックあたり約115mg)を多く摂取するほか、ビタミンDの吸収を助けるビタミンK、そして血栓を予防する酵素「ナットウキナーゼ」も同時に補うことができます。
私にとって理想的な一日は、朝に納豆をいただき、昼か夜には鰻を楽しむ――そんな栄養たっぷりで心も満たされる食事ができる日です。
鰻(うなぎ)に含まれるマグネシウムの量と栄養素

「鰻=栄養満点」「鰻=精がつく」というイメージはあるものの、実際にどのような成分が含まれているのかは意外と知られていません。
ここでは、鰻の栄養価を見ていきましょう。
鰻(うなぎ)の栄養成分
鰻の蒲焼き(100gあたり)には、15mg程度のマグネシウムが含まれています。
マグネシウムと一緒に摂取したいカルシウムの含有量は150mg程度、カリウムの含有量は300mgと、魚類の中でもミネラルの含有量が高い部類に入り、栄養バランスに優れた食材といえます。
そのほかにも、ビタミンA、ビタミンB群(B1・B2・B12)、ビタミンE、DHA・EPAといった必須脂肪酸、鉄やカルシウム、亜鉛などのミネラルも豊富に含まれており、夏場に乱れやすい体内バランスを整えるにはぴったりの食材です。
鰻(うなぎ)の脂は良質な油
鰻は脂がのった魚というイメージが強く、「太りそう」と敬遠する方もいるかもしれません。
しかし実際には、鰻の脂にはオメガ3脂肪酸であるDHAやEPAがたっぷり含まれており、血液をサラサラにしたり、脳の働きを活性化したりなど、健康をサポートする栄養素が豊富です。
また、ビタミンAやEといった脂溶性ビタミンの吸収を助ける働きもあり、抗酸化作用にも期待できます。
また、鰻を焼く時のあの食欲をそそる良い香りもまた、鰻の脂によるものです。
実際に含まれる栄養素も大切ですが、食欲が低下しがちな夏だからこそ、「食欲をそそる香り」はとても魅力的。
豊富な栄養素と、唯一無二のあの「おいしそうな香り」こそ、鰻の魅力といえます。

鰻(うなぎ)で得られるマグネシウムのメリット
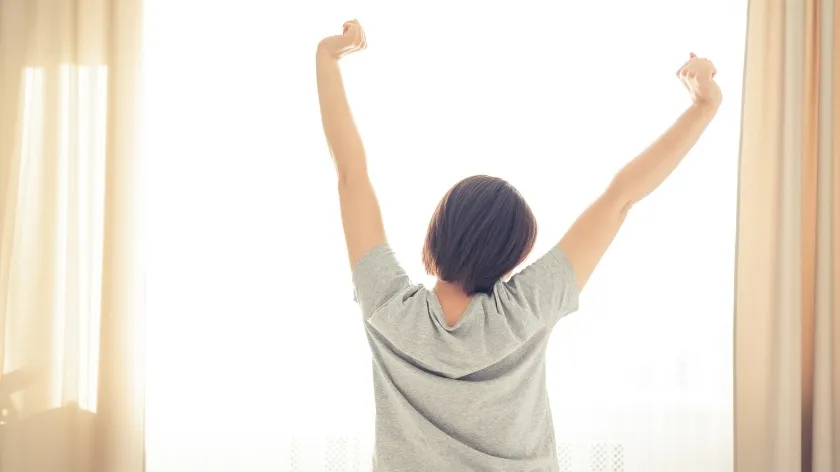
では、鰻に含まれるマグネシウムをしっかり摂ることで、私たちの体にどんなメリットがあるのでしょうか?
ここからは、マグネシウムの働きをご紹介します。
疲労回復
マグネシウムは、人間が生きる上で必要とするエネルギーを生み出すATP(アデノシン三リン酸)の産生に必要不可欠な栄養素です。
「疲れやすい」「体が重い」といった症状はエネルギー不足に由来する場合が多く、マグネシウムが不足しているとスムーズに代謝が回らなくなってしまいます。
そんな時は、鰻などミネラルを豊富に含む食べ物を食べて体内のマグネシウムレベルを高め、代謝を活性化させるのが理想です。
代謝が活性化されるとエネルギー効率が高まり、夏バテによる疲労感や倦怠感などを改善しやすくなります。
もちろんマグネシウムで構成されたサプリメントや、エプソムソルト(硫酸マグネシウム)を活用した入浴法などで、マグネシウム不足を予防するのも効果的です。
ストレスや不眠対策
マグネシウムには、精神的なイライラや心身の緊張状態を和らげるなど、神経を鎮める働きがあるとされています。
また、睡眠の質にも深く関わっており、マグネシウムを十分に摂取してリラックスした状態を作ることで、眠りやすくなることがわかっています。
夏は寝苦しく、夜間の目覚めも多くなりがちですが、鰻に含まれるマグネシウムやビタミンB群は、安眠のサポートに効果的です。
身体機能のサポート
筋肉の収縮や神経の伝達、体温の調整など、マグネシウムは体内でさまざまな役割を担っています。
特に暑さによって自律神経が乱れやすい季節には、マグネシウムが心強い味方になります。
骨の健康維持にも必要な栄養素なので、子どもから高齢者まで、年齢に関わらず積極的な摂取を心掛けたいところです。
鰻(うなぎ)の上手な取り入れ方と注意点

体に良いからといって、鰻を毎日食べれば良いわけではありません。
鰻の栄養価を効果的に、かつ安心して取り入れるための注意点も押さえておきましょう。
ビタミンAの過剰摂取に注意
鰻は各種ミネラルのほか、ビタミンAの含有量が高い食材でもあります。
ビタミンAは脂溶性のため、過剰に摂取すると体に蓄積され、頭痛や吐き気、肝機能障害などを引き起こす可能性も。
特に妊娠中の方やサプリメントを併用している方は、鰻の食べ過ぎに注意しましょう。
鰻を食べる目安としては、週に1〜2回程度が理想です。
食べ合わせによる消化不良に注意
鰻は脂質が多く、消化に時間がかかるため、食べ合わせにも工夫が必要です。
たとえば、冷たい飲み物や果物など、水分を多く含むものと一緒に食べると消化器に負担がかかり、胃もたれや不調の原因になることも。
水と脂を同時に摂取するのは胃腸への負担が大きく、消化に余計なエネルギーが要されることから、疲労感や倦怠感を助長する可能性があります。
逆に、山椒や大根おろし、梅干しなどの消化をサポートする食材と一緒に食べると、体に優しい組み合わせになります。
鰻(うなぎ)の豆知識

せっかく鰻を食べるなら、ちょっとした豆知識を知っておくと楽しいですよね。
最後に、意外と知られていない鰻に関する豆知識をいくつかご紹介します。
鰻(うなぎ)はいつから食べられるようになった?
鰻は、古くから食べられている歴史の長い食文化です。
奈良時代の文献「万葉集」にもその記述が見られ、平安時代には薬膳として用いられていたそうです。
江戸時代に入って、私たちがよく知る「鰻のかば焼き」の形が普及し、庶民の間に広まりました。
特に夏の暑さに負けないためのスタミナ源として重宝されてきた歴史があります。
とはいえ、鰻の本来の旬は秋~冬というのも面白いところ。
最近は鰻の養殖技術がようやく確立され、季節を問わずに楽しめる可能性が高まってきました。
土用の丑の日ってなに?
「土用」とは、季節の変わり目の約18日間を指し、「丑の日」は干支で日を数える中の一日を指します。
この二つが重なる日を「土用の丑の日」と呼んでいます。
江戸時代、平賀源内(江戸時代の医者および学者)の発案で「丑の日に“う”のつく食べ物を食べると夏負けしない」というキャッチコピーが広まり、鰻が定着したといわれています。
鰻(うなぎ)に山椒をかける理由
鰻には欠かせない薬味「山椒」。
ピリッとした辛味と爽やかな香りが鰻との相性抜群の山椒ですが、実は単に「鰻と合う味だから」という理由で定番になっているわけではありません。
鰻には脂が多いため、人によっては胃もたれを起こしやすい食べ物です。
そこで、胃腸機能をサポートし消化を助ける働きがある山椒を合わせて、鰻の脂の負担の軽減を図る工夫がされたのです。
また、山椒には健胃・消化促進のほか、抗菌作用もあるとされています。
鰻(うなぎ)を食べると精がつく?
「鰻は精がつく」という言葉も、実は栄養学的な裏付けがあります。
鰻にはタンパク質、ビタミンE、亜鉛、マグネシウムなど、男性ホルモンの分泌を助けたり、疲労を回復させたりする栄養素が多く含まれています。
暑さで体力が奪われがちな夏には、まさにぴったりの食材と言えるでしょう。
ただし、食べすぎると先述したようにビタミンAの過剰摂取のリスクや、胃腸への負担リスクが生じます。
食べ合わせに気をつけながら、適度に楽しむのがおすすめです。
まとめ|鰻(うなぎ)とマグネシウムで酷暑を乗り切ろう!

暑さから体を守るには、日々の食事からの「ミネラル補給」が欠かせません。
特に夏バテや疲労感、ストレスを緩和するのに心強い味方となるのが「マグネシウム」です。
滋養強壮の代名詞ともいえる鰻は、昔ながらの知恵だけでなく、現代の栄養学にもかなったパワーフードで、マグネシウムをはじめさまざまなミネラルを含んでいます。
暑さが厳しい季節には、週に1度でもいいので、鰻を食卓に取り入れてみませんか?
体に優しく、食欲を駆り立ててくれる鰻を、酷暑を耐える自分や家族へのご褒美として、週に1度程度の頻度で食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。